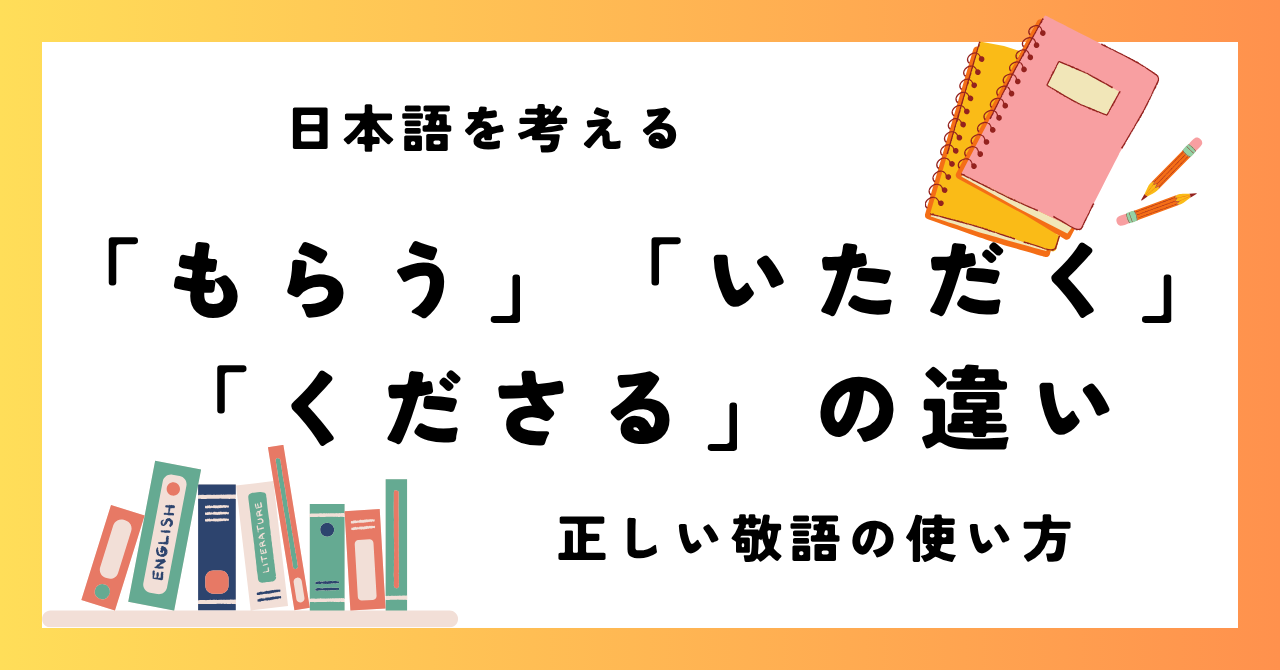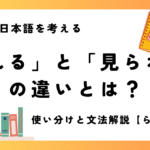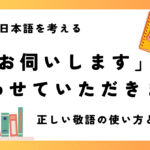敬語とは、単に相手に丁寧さを示すためのツールではありません。
それは、日本語における〈他者との距離感〉を繊細に表現するための、美意識にもとづいた言葉遣いなのです。
たとえば、誰かから何かを「もらう」とき。
私たちは「ありがとう」という感謝の言葉とともに、「もらう」「いただく」「くださる」といった語の中から、最もふさわしい表現を選ぼうとします。
その選び方ひとつで、相手への敬意が自然に伝わるかどうかが決まります。
だからこそ、似た意味の言葉でも使い方を間違えると、かえって不自然に響いてしまうことがあるのです。
この記事では、「もらう」「いただく」「くださる」の違いを軸に、それぞれの正しい使い分け方を文例とともに解説します。
「もらう」「いただく」「くださる」の基本的な違いとは?
「もらう」は“私”が主語
「もらう」は、相手から何かを受け取ることを意味する、最も一般的な表現です。
例:友だちからチョコをもらった。
例:先生に教科書をもらう。
この語の特徴は、「私」が主語であり、「相手から何かを受けた」という視点に立っている点です。
ただし、「もらう」は敬語ではありません。あくまで中立的な口語表現。
ビジネスやフォーマルな場面では、より丁寧な言い換えが求められます。
「いただく」は“自分がへりくだる”敬語(謙譲語)
「いただく」は、「もらう」の謙譲語です。
自分がへりくだることで、相手を立てる敬語表現となります。
例:上司に資料をいただきました。
例:お客様からご意見をいただく。
このように、「私」が何かを受け取った行為をへりくだって述べることで、相手への敬意を示しています。
目上の人や取引先とのやり取りでは、「もらう」ではなく「いただく」を選ぶのが適切です。
また、「いただく」は「食べる」「飲む」の謙譲語としても使われます。
例:昼食をいただきました。
「くださる」は“相手が主語”の敬語(尊敬語)
一方、「くださる」は「くれる」の尊敬語で、相手の行為そのものに敬意を込めて表す言葉です。
例:先生が本をくださいました。
例:社長が直接アドバイスをくださった。
重要なのは、「くださる」はあくまで相手の行為に対して使う尊敬語であるということ。
自分の行為には絶対に使いません。
また、文の主語と述語の敬語の種類が一致しているかも確認しましょう。
誤:部長から資料をくださった。
正:部長が資料をくださいました。
使用シーン別の使い分けガイド(例文付き)
日常会話での使い分け
日常では、相手との距離感や関係性によって自然な使い分けがなされます。
たとえば、親しい友人には:
「この前、誕生日プレゼントをもらったんだ。」
と、「もらう」で問題ありません。
しかし、目上の人には:
「先生からプレゼントをいただきました。」
または
「先生がプレゼントをくださいました。」
といったように、相手の立場や視点に応じた表現を選びましょう。
ビジネスシーンでの使い分け
ビジネスメールや電話対応など、フォーマルな場ではさらに丁寧な表現が求められます。
【例:資料を受け取った場合】
- ✕ 資料をもらいました
- ○ 資料をいただきました
- ◎ 資料をお送りいただき、誠にありがとうございます
また、相手の行為に感謝を伝えるときは:
「お忙しい中、貴重なご意見をくださいまして、ありがとうございました。」
といったように、「くださる」を使うと自然に敬意を表せます。
NGな使い方とその理由
【誤用例1】
お客様が資料をいただきました。
→「いただく」は謙譲語のため、自分側の行為に使うべきです。
この場合は尊敬語を使って:
お客様が資料をお受け取りになりました。
【誤用例2】
私がプレゼントをくださった。
→「くださる」は相手の行為を高める表現なので、自分には使えません。正しくは:
私がプレゼントをいただきました。
敬語は「誰が主語か」「誰の行為か」を見極めることが大切です。
自然な敬語を使うコツ
敬語を丁寧にしようとするあまり、かえって不自然な表現になることもあります。
たとえば:
「○○様よりお電話を頂戴いたしましたことを深く御礼申し上げます。」
このような表現は場面によっては「過剰敬語」と受け取られる可能性もあります。
敬語の本質は「相手を思いやる気持ち」です。
見た目の丁寧さにとらわれすぎず、状況に応じた自然な表現を心がけましょう。
- 相手の行為には尊敬語(くださる)
- 自分の行為には謙譲語(いただく)
- カジュアルな場面では丁寧語(もらう+です・ます)
この基本を押さえるだけでも、敬語の使い分けは格段にしやすくなります。
おわりに
「もらう」「いただく」「くださる」は、似た意味をもちながら、それぞれに異なる視点と敬意の向きがあります。
敬語は単なる“ルール”ではありません。
それは、相手をどう見るか、どのような距離感で接するかという〈心の姿勢〉を言葉に込める、日本語独自の感性です。
敬語の正しさは知識だけでは測れません。
「どう言えば、この人に気持ちが伝わるだろう」——その思いやりこそが、自然で心ある敬語を生み出します。
言葉の向こうにいる“相手”を大切に思いながら、今日も丁寧な言葉を選んでいきましょう。