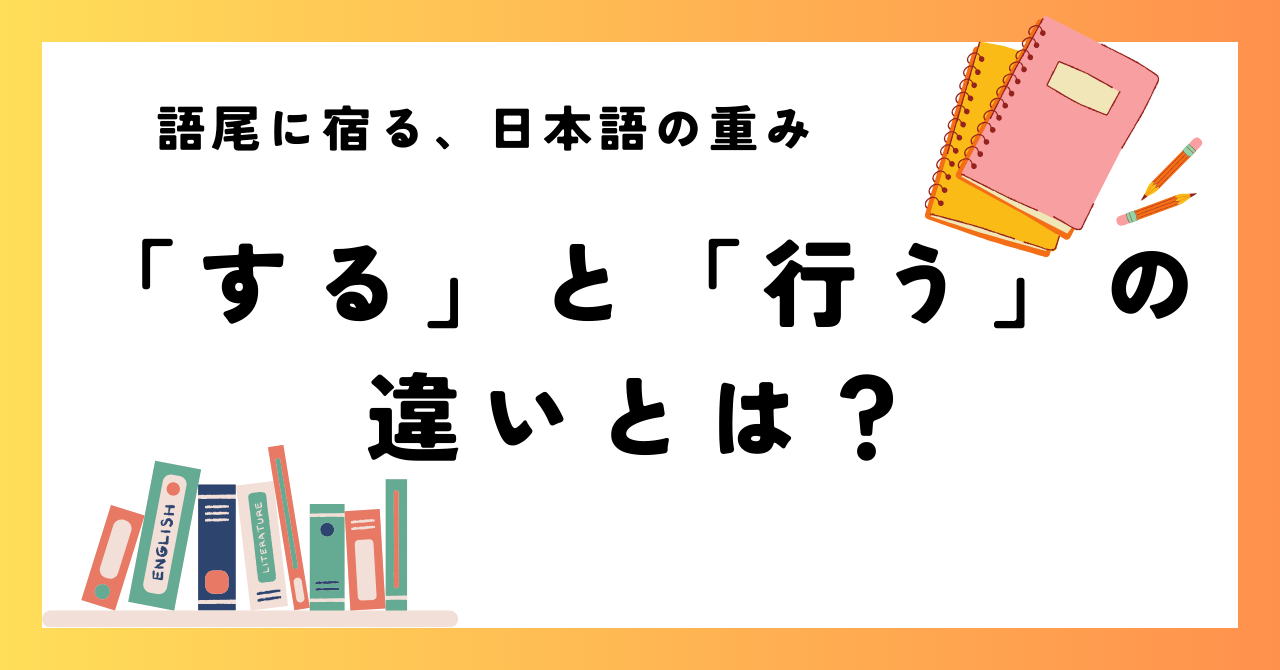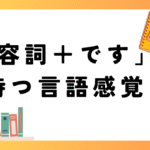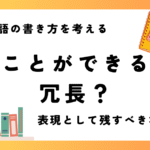文章を書いているとき、ふと、語尾に引っかかることがある。
たとえば「調査を行う」「確認を行う」「手続きを行う」――整っているようでいて、どこか息苦しい。必要以上に改まった響き、語尾に漂う重たさ。簡潔に「調査する」「確認する」とすればよいのに、なぜ「行う」という言葉を選んでしまうのか。
言葉には「言い換え」がある。だがその選択の違いには、書き手の無意識が宿る。今回は、「〜を行う」という表現に焦点を当て、冗長さと曖昧さの正体を探りつつ、それでもなお「行う」を選ぶ意味について考えてみたい。
第1章:「〜を行う」は、なぜ使いたくなるのか
「〜を行う」は、万能だ。
どんな名詞にもつけられる。「検討を行う」「報告を行う」「作業を行う」……。一見丁寧で、書き手の距離感も保たれていて、安全な言い回しに思える。
この表現は、ビジネス文書や官公庁の発表、報告書、論文などで頻繁に使われている。文書全体に整った印象を与えるため、実務上も便利な表現であることは確かだ。
だが、私たちはなぜそれを「安全」だと感じるのか。
おそらく、「直接的すぎない」からだろう。「検討する」と書けば、主体と行為が直結し、生々しさが残る。「検討を行う」とすれば、少しだけ視点が引かれ、どこか“決まり文句”として処理される。
つまり、「行う」は、行為の熱を冷ます。
そして、冷めた言葉は、責任の所在をぼかす。
私たちは、自分が何かを「する」ことに、どこかで怯えているのかもしれない。だからこそ、「行う」というクッションを置く。あえて距離を取り、丁寧さを装う。その裏に、書き手の迷いが透けて見える気がする。
第2章:冗長な「行う」が曖昧にするもの
たとえば次のような文があったとする。
・現地調査を行いました。
・本人確認を行ってください。
・業務の見直しを行います。
これらは、単に「調査しました」「確認してください」「見直します」で事足りる。むしろ簡潔な方が自然で、情報も明快だ。
「行う」を挟むことで何が起きるか。それは、
- 文が重くなる(テンポが鈍くなる)
- 行為の実体が曖昧になる
- 誰がしたのか/するのかが不明確になる
「見直しを行います」と言ったとき、誰が見直すのか、どんな風に見直すのか、そのリアリティは希薄になる。「見直します」であれば、主体が立ち、責任が浮かび上がる。
言葉は、本来、明快であるべきだ。もちろん詩や文学には曖昧さが美しく映える瞬間があるが、少なくとも報告や説明、実用文においては、曖昧さは読み手を混乱させるだけのものになる。
便利な表現ほど、思考を止めてしまう。冗長な「行う」に慣れてしまった文章は、やがて書き手と読み手の距離感を鈍らせていく。
第3章:「行う」の言い換えパターン――例とともに
では、「〜を行う」をやめたいとき、私たちはどんな言葉を選べばよいのか。
以下にいくつかの代表的なパターンを挙げてみる。
| 元の表現 | より適切な言い換え | 理由 |
|---|---|---|
| 実験を行う | 実験する/実験を実施する | 「実験する」で簡潔に、「実施」で公的文書向け |
| 会議を行う | 会議を開く/会議を開催する | 「開く」で柔らかく、「開催」で形式的に |
| 処理を行う | 処理する/処理を実行する | 技術的なら「実行」が適切 |
| 対応を行う | 対応する/対応にあたる | 実務的な表現に寄せる |
| 調査を行う | 調査する/調査を実施する | 文脈により調整可能 |
こうした言い換えによって、文章はぐっと引き締まる。そして何より、読み手の理解が早くなる。これは単に語数の問題ではない。言葉の動きの問題だ。冗長な動詞は、文章全体の筋肉を弱くする。筋肉を鍛えるには、より具体的で動きのある動詞を選ぶ必要がある。
第4章:「行う」にしか出せない響きもある
それでもなお、「行う」でなければならない場面はある。
たとえば次のような言い回し。
- 神前にて、結婚の儀を行う。
- 手術を行う。
- 国家によって裁判が行われる。
こうした場合、「する」では軽すぎる。言葉には重さと儀式性が必要なときがある。「行う」は、ただの行為ではなく、儀礼、制度、手続きのような格式をまとっている。
また、法律文や公文書では、「行う」が最も正確で中立な言い回しになる。感情を排し、形式的な正しさを重んじる世界では、「する」ではラフすぎるのだ。
要は、「行う」が悪なのではない。問題は、それをどこでも使ってしまう“惰性”である。
私たちが書く言葉には、必ず文脈がある。その文脈において、「行う」が本当にふさわしいのか。それを問い続けることが、書き手としての矜持につながる。
第5章:語尾を選ぶということ
言葉の“語尾”は、意外と読者の印象を左右する。そこで文の温度が決まる。
「〜を行う」は、たしかに整っている。だがその整いの中に、何かを失ってはいないか。私たちの文章は、いつのまにか“無難”という鎧をまといすぎてはいないか。
言葉を選ぶとは、心の姿勢を選ぶことだ。
「する」か「行う」か――その選択に、正解はない。ただ、どちらが適切かを常に考え続けることで、言葉は強くなっていく。そして、その強さは必ず読み手に伝わる。
結局のところ、語尾に宿るのは、文体の品格であり、書き手の誠意なのだと思う。
結びに代えて:あなたの文章に「行う」はいくつあるか
最後に一つ、問いかけたい。
あなたの最近書いた文章には、「行う」がいくつ登場していただろうか? そのすべてが本当に「行う」である必要があっただろうか?
文章は、読み手に届けるためにある。その言葉は、読みやすく、的確で、必要最低限であるべきだ。だからこそ、「行う」という言葉が、本当にその一文にふさわしいのか、一度立ち止まって考えてみてほしい。
それは、小さな問いに見えて、文章全体の質を変える大きな分かれ道なのだから。
▶関連リンク・おすすめ記事