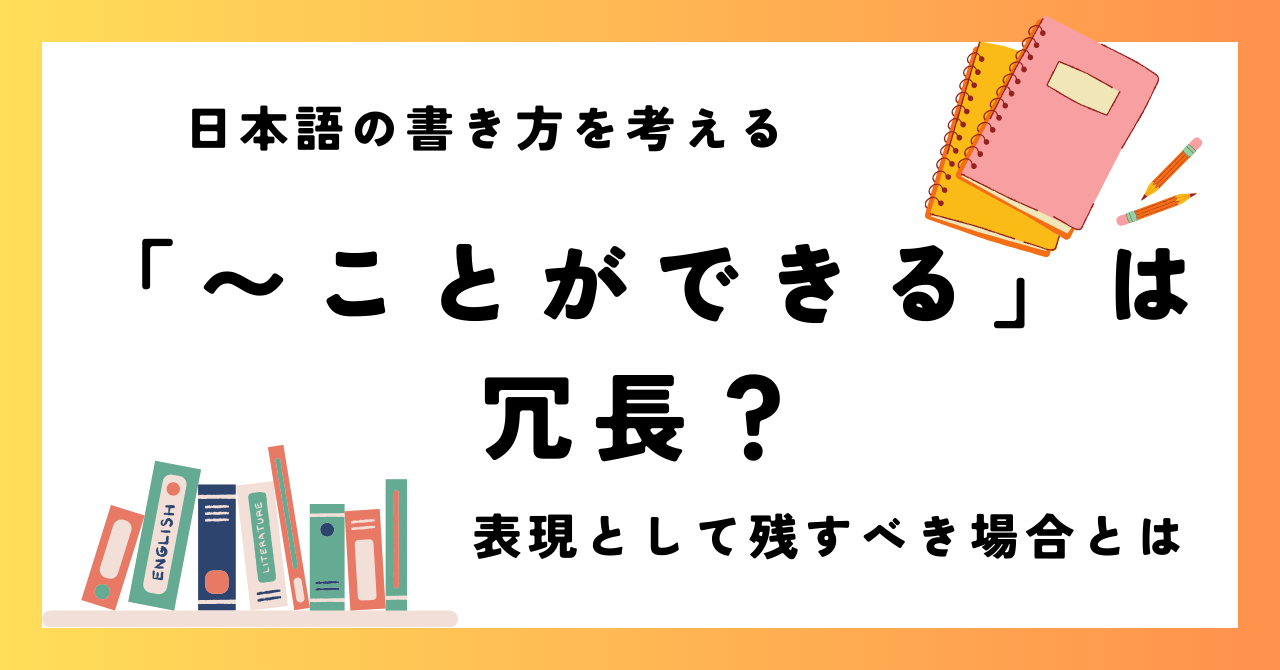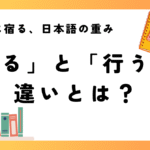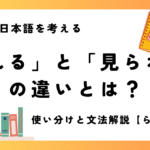私たちの文章は、いつから「できることができる」ようになってしまったのだろう。
たとえば、こんな一文。
この本を読むことで、人生について考えるきっかけを得ることができる。
きっと丁寧に、親切に書かれた文章だ。読者の理解を助けるように、言葉を尽くした結果なのだろう。けれど、どこか息苦しい。主語は不在のまま、「こと」が二度も現れ、文の輪郭を曖昧にしている。まるで、言いたいことに手が届きそうで届かない──そんなもどかしさが残る。
それでもこの言い回しは、ビジネス文書でも、解説記事でも、学校の作文でも、あらゆる場所で目にする。「〜ことができる」は、便利な言葉だ。語調はやわらかく、意味も明確。誰かを傷つけるわけでもない。けれど、その便利さに甘えていると、文章はいつのまにか重たくなり、書き手自身の身体からも、心からも、少しずつ遠ざかっていく。
この記事では、「〜ことができる」という言い回しについて、削るべきとき、残すべきときを考えてみたい。言葉の輪郭を取り戻したいと願うすべての書き手に向けて。
「ことができる」はなぜ冗長と言われるのか?
「〜ことができる」は、もともと「動詞+名詞化+可能表現」の構文です。たとえば「読む」→「読むこと」→「読むことができる」となるわけですが、この構造自体がすでに一歩遠回りです。
この資料を読むことができる
→ この資料が読める
というふうに、「読むことができる」を「読める」に言い換えれば、よりすっきりした表現になります。日本語には、動詞に「可能の助動詞(られる)」をつけるだけで十分に意味が伝わる表現が多く存在します。にもかかわらず「ことができる」と言いたくなるのは、丁寧に見せたいからか、あるいはリズム的な癖なのかもしれません。
しかし、丁寧さのつもりが、かえってもたついた印象や言い回しの重複を生んでいることもある。文章の緊張感が緩み、要点が霞んでしまう危険を含んでいます。
それでも「ことができる」が必要なとき
とはいえ、「冗長だから削っておしまい」というほど、この言い回しは単純でもありません。
たとえば、次の二文を比較してみましょう。
・この展示では、江戸時代の風俗画を見ることができる。
・この展示では、江戸時代の風俗画が見られる。
後者の「見られる」には、やや事務的な響きがあります。一方、前者の「見ることができる」には、「可能である」という状況の説明が丁寧に伝わってきます。また、「〜することができる」は、やや柔らかい語調を持っており、語調の緩衝材としても働きます。
あるいは、比喩的な表現と組み合わせると、詩的な響きが生まれることもある。
この詩を読むことで、声なき声を聴くことができる。
このときの「聴くことができる」は、単なる能力ではなく、「静かに耳を澄ませば、かすかなものが伝わってくる」ような、行為以上の感受性をまとっています。「〜ことができる」には、行為の背後にある可能性や感受の幅まで含めることができるのです。
判断基準と言い換えのヒント
では、どんなときに「ことができる」を削ってもよく、どんなときに残すべきなのでしょうか。以下のような視点が参考になります。
削ってよいケース
- 「読むことができる」→「読める」
- 「参加することができる」→「参加できる」
- 「作成することができる」→「作成できる」
冗長さを避けたいときは、動詞+可能表現(〜れる、〜られる)へと簡潔に言い換えましょう。
残す価値があるケース
- 柔らかい表現にしたい(「〜ことができる」は丁寧)
- 詩的な表現の余白を持たせたい
- 「Aすることも、Bすることもできる」のように並列構造で使いたい場合
- 「可能性」と「許可」の両義をふくませたい場合
たとえば、
あのとき、私は泣くことができなかった。
→ あのとき、私は泣けなかった。
この言い換えは意味が似ていても、語感はずいぶん異なります。前者は内面の葛藤を引きずるような感触があり、後者は少し乾いた響きをもつ。だからこそ、詩や小説の文体では「ことができる」が生きる場面も多いのです。
書き手の文体が、最終判断をくだす
結局のところ、「ことができる」は敵でも味方でもありません。要は、「なぜこの言葉を選んだのか」という意識が、書き手にあるかどうか。
自分の文章のなかで、「ことができる」はどこまで意識されているか。その言い回しが必要なのか、あるいは無意識の繰り返しなのか。表現を削るときは、意味の省略ではなく、意図の明確化として行いたい。
言葉のひとつひとつに意図を宿らせる。そうして生まれた文章は、読者の呼吸とすこしずつ重なっていくのです。
結びにかえて
言葉は、できるだけ、でいいのか。それとも、できることを、あえて書くのか。
あなたの「ことができる」は、どちらだろうか。
▶関連リンク・おすすめ記事