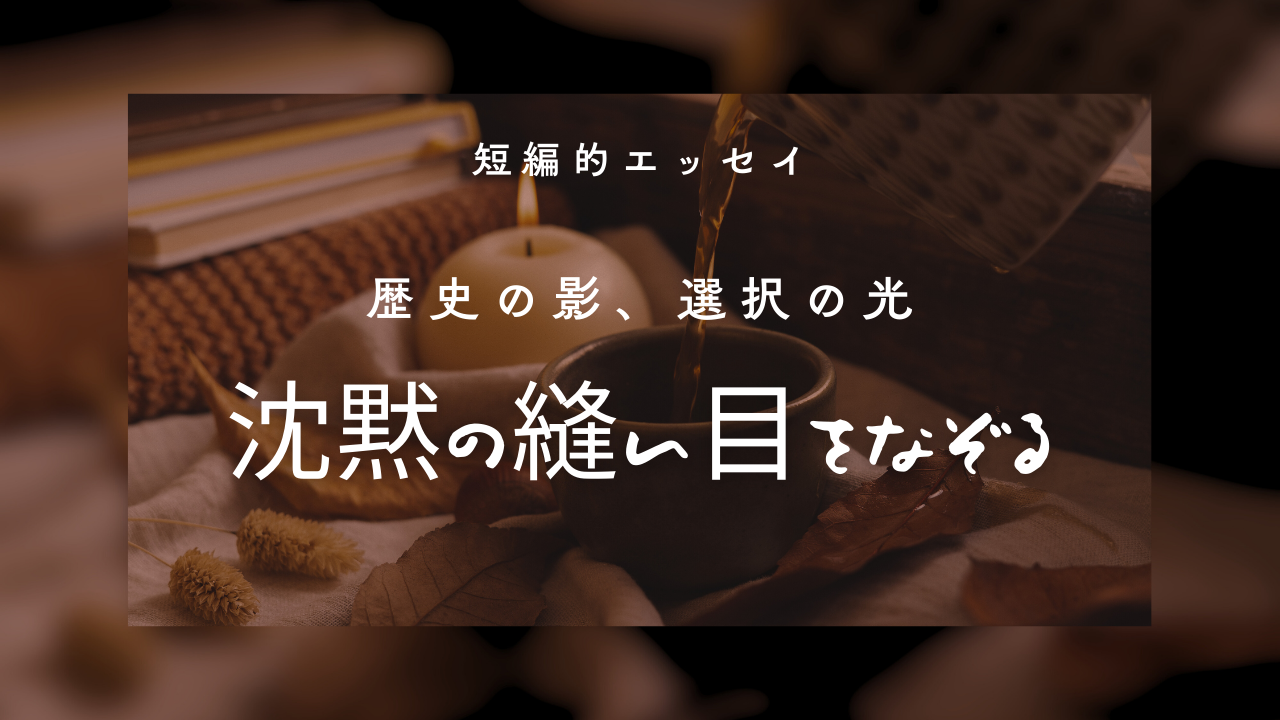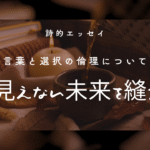テレビの音だけが、灯りの代わりのように部屋を満たしていた。
午後のニュース特番。国会中継。
乾ききらない洗濯物が、天井のハンガーから湿った気配を落としている。
画面の向こうでは、誰かが問い、誰かが答えている。
質疑というより、ただ寄せては返す波のようだった。
「台湾有事」
その四文字を耳にした瞬間、手にしていたマグカップを静かに机へ置いた。
まだ起きていないはずの出来事なのに、どこか既視感のある影が、部屋の隅に忍び込んだ気がした。
――もし明日、それが起きたら。
政治評論家の声が遠のき、代わりに紙の擦れる音が戻ってくる。
机に積まれた資料には、法制度や同盟、憲法の文字が整然と並んでいた。
整然としているからこそ、その隙間に縫い付けられた迷いの跡が見えてくる。
選ぶということは、正義を持つことではなく、
迷いを抱えたまま歩くことなのかもしれない。
*
夜。風呂上がり、鏡の前で髪を乾かしながら、ふいに昔の授業を思い出した。
「保守」「改革」「中道」。
黒板に書かれた三つの言葉は、当時はただの位置関係に見えていた。
今は、あのときよりも少し違う輪郭で立ち上がる。
伝統を守ろうとする者。
新しい扉を叩く者。
その間に立ち、椅子を並べようとする者。
中道とは真ん中ではなく、
両側の水位を測りながら、小さな舟を出す場所なのだろう。
沈黙は従属ではなく、選択のひとつだ。
そんなことを思った。
*
本棚の前に立つ。
ふと手が伸びたのは、火野葦平の『麦と兵隊』だった。
その隣にある永井荷風の日記。
昔つけた付箋が、かすかに黄ばんでいる。
国家が大きな渦のように押し寄せた時代、
彼らはどんな顔でそれを見つめていたのだろう。
抗い、流され、身をかわし、それでも書いた。
どれが正しかったのか、私たちはつい問いたくなるけれど、
その問いの鋭さが、時に残酷だということも分かっている。
選ばなかった道は紙面に残らない。
それでも胸のどこかに、痕跡のように灯り続ける。
*
その日、使い終えたポットの裏をふと見てしまった。
小さな印字が目に入る。
Made in China.
日本のメーカーだが、製造は中国。
ずっと見慣れた組み合わせだ。
蛍光灯の白い光がわずかに揺れた。
国境を越えて届いた家電。
どこかの工場の灯り。
そこで働く誰かの手の温度を、私は知らない。
「どこで作られたものかを気にする」という行為は、
遠くの誰かの生活に、一瞬だけ触れようとする小さな身振りなのかもしれない。
*
眠れず、ベッドに横たわる。
今日見たニュースが、ゆっくりと頭の中で巻き戻される。
国家も、歴史も、産業も、自分には大きすぎる。
その大きさに圧倒される一方で、私が選べるものは、手元の些細な選択だけだと知る。
どんな情報に目を向けるか。
どんな言葉を拾うか。
どんな商品を手に取るか。
静かで、誰にも気づかれない選択でも、
積み重なれば、どこかで波紋になるのだろう。
迷ったままで、いい。
選びながら、また学び直す。
その揺らぎの中で、私は生きていく。
画面の電源を切ったあとの暗がりで、
手のひらに残ったわずかな温度だけが、妙に確かだった。