J-P・サルトル氏の『実存主義とは何か』を紹介します。
「自由、不安、不条理、実存」はサルトルの文学、哲学の鍵
J-P・サルトル氏の『実存主義とは何か』は、伊吹武彦氏の訳で1955年7月に人文書院より刊行された。これは、1945年に当時41歳のサルトルが行った講演とそれにつづく討論であり、その講演内容が1946年に出版されたもの。さらに1996年1月の増補新装版では、サルトルの初期作品五点が増補された。
伊吹氏のあとがきによると、『実存主義とは何か』のもとの題名「L’Existentialisme est un humanisme」を直訳すれば、「実存主義はヒューマニズムである」となるが、これを表紙の題名にすると長すぎるので改題したとのこと。本文の小見出しでは、「実存主義はヒューマニズムである」が採用されている。
サルトルは、1945年の講演で実存主義の本質を伝え、その思想がヒューマニズムに直結することを説く。当時、実存主義という言葉が、議論の的となりつつあった。その本質をサルトルはできるだけ平易かつ明快に叙述した。
増補新装版で増補された五作品は、実存主義の発想が具体的に示されている。いずれもミッシェル・コンタ、ミッシェル・リバルカ編の『サルトルの著作』に収録されている作品。題名は「糧」「偉人の肖像」「顔」「実存主義について ―― 批判に答える」「パリ解放・黙示録の一週間」。さらに、本書のはじめに「1945年の実存主義」と題した、海老坂武氏による解説がある。
サルトルは、戦前に発表した文学作品の『嘔吐』や『壁』においてある程度の読者を得てはいたし、戦争中に上演され話題を呼んだ『蠅』や『出口なし』という芝居の原作者でもあった。しかし、講演会の日までのサルトルは、決して有名人ではなかった。にもかかわらず、講演会場は超満員となり、新聞各紙は大きなページをあてたのはなぜか。
それを解く鍵のひとつは、講演の題名にある実存主義という言葉であった。サルトルはまだ流行作家になってはいなかったが、実存主義者という言葉がジャーナリズムのあいだで飛び交っていた。しかも、ほとんどの場合はマイナス・イメージが付着していた。実存主義者とは、パリのサン・ジェルマン・デ・プレの界隈にたむろしている二十歳前後の若者たちを指していた。
では、講演が行われた1945年はどういう時代だったのか。ご存じの通り1945年のフランスは、4年間続いたナチス・ドイツの占領から抜け出したばかりであった。当時の若者たちの行動の原因は、「戦争も占領も解放さえも、古い価値観を奉ずる大人たちの世界が起こしたものではないか」という、不条理に対する反抗にあったと解することができる。とすると、サルトルの哲学までの距離はそう遠くはない。なぜなら、「自由、不安、不条理、実存」という言葉は、サルトルの文学、哲学の鍵なのだから。
そして、起源ははっきりしないが、サン・ジェルマン・デ・プレの若者たちを、文学・哲学の事情通が実存主義者と名付けたようだ。また、サルトル自身も、この界隈でホテル住まいをし、仕事をし、ときには若者を集めて議論するという生活をしていた。
しかし、サルトルからすれば、自分の哲学と若者の行動を結び付けられるのは迷惑だったはず。サルトルは、1945年の講演の中で、混同に釘をさそうとし、当初は実存主義という名称を拒否していた。だが、ある時期からこの言葉を引き受ける姿勢を取り始めた。
1945年には新鮮に見えた、「主体性、選択、投企、不条理、アンガジュマン(自己拘束、社会参加)」も、新鮮さは薄らいできたかもしれない。たとえば、主体性によって価値を選んでいくことは、ある程度、常識になったといえよう。しかし、講演そのものが、一般聴衆に対するものということで、サルトルは実存主義をかなり通俗化して紹介した。そのため、講演だけでサルトルの実存主義を論じるのはやや無理があると、海老坂氏は述べている。そこで海老坂氏は、「1945年の実存主義」と題して解説も加えた。
実存の観念は、「少年期からのサルトルの生体験のレベルに位置し、世界と人間に対する根源的なビジョン」に発している。そのことは、初期の小説『嘔吐』が示している。『嘔吐』は、サルトルが10年の歳月を費やし、1938年に刊行された作品であるが、実存主義の原点が見えてくる。
海老坂氏によれば、『嘔吐』とは一言で言うなら、「主人公のロカンタが嘔き気の体験をとおして事物と人間の存在を発見する物語」。この実存の発見は、我々の世界と我々自身が、「偶然であり、不条理であり、無償であり、余計な存在である」という認識に通じていく。そしてこの認識はやがて「人間は自由だ」というもう一つの認識、楽観主義的な言説へと通じていく。
1945年以後、サルトルの実存主義は三つの方向に展開した。第一に、「マルクス主義にとってかわって、あるいはマルクス主義の諸原理を吸収して、社会変革の指導的イデオロギー」たろうとした。第二に、「アンガジュマンの文学の実践と理論化」。第三は、人間理解の方法としての実存的精神分析の展開であり、フロイトの精神分析とは異なる解釈体系を打ち立てようとする試みであった。
サルトルは、『文学とは何か』(1947年)を上梓しており、その中で文学作品を、「人間の自由を要求するかぎりでの世界の想像による表現」と定義した。ただ、文学についての考え方は、時代とともに変化している。重視する視点が、政治的、社会的姿勢からエクリチュール(書き方)へと変化したようだ。
実存主義の文学観の特徴としては、二つのポイントがある。一つは「文学作品とは描く対象が自己であれ、他人であれ、社会であれ、歴史であれ、最終的には作者の生体験がそこに深く刻まれており、したがって、作者の生と作品とを切り離して考えることはできない」ということ。もう一つは「自己の全体」を表現することであるが、「一人の人間は、ある時代の社会にその人間に固有の歴史をになって生きている」のであるから、それを表現する作家は、人間諸科学の知を必要とする。
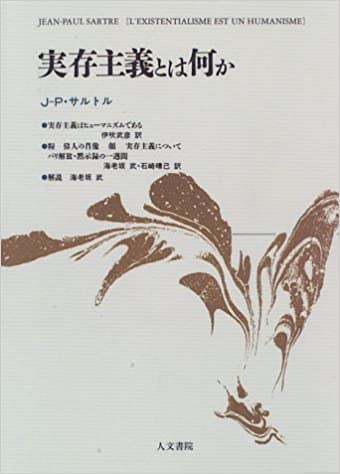
書誌情報
書名:実存主義とは何か
著者:ジャン=ポール・サルトル
翻訳:伊吹武彦・海老坂武・石崎晴己
出版社:人文書院
発売年月:単行本 1955年7月/単行本(増補新装版) 1996年1月
ページ数:単行本(増補新装版) 180ページ
Cコード:C1010(哲学)


