ジャン=ポール・サルトル氏の小説『嘔吐』について、そのテーマや登場人物、物語の魅力をさまざまな角度から掘り下げていきます。
20世紀十大小説の一つ
『嘔吐』は1938年3月、サルトルが三十三歳のとき、フランスのガリマール書店から刊行された。1931年11月から、「偶然性に関する公開状」という題の本の執筆に取り掛かり、これがのちに『嘔吐』となった。原題「La Nausée」を内容に即して訳せば、嘔気、あるいは吐き気となるが、白井浩司氏は活字体の効果を考えてあえて、嘔吐とした。サルトルの『嘔吐』は、20世紀十大小説の一つと評されている。
冒頭では、ルイ=フェルディナン・セリーヌの小説『教会』からの引用、「カストールに捧ぐ」という献辞に続き、刊行者による前書きという形での脚色がある。前書きの内容は、アントワーヌ・ロカンタンという人物の書類の中から発見されたノートを、いっさい手を加えずに刊行するというもの。このノートは日記である。本作は、青年ロカンタンの日常を、内的独白と細かな心理描写で展開させた。
サルトルは、1931年の秋からル・アーヴルの高等中学校で哲学を教えていたが、その数年間、北フランス最大の工業都市に滞在していた。『嘔吐』の舞台であるブーヴィルは、この港湾都市をモデルにしたのであろう。<存在>についての掲示を得た公園での、マロニエの樹をめぐっての考察も、そこでの体験であった。
「偶然性に関する公開状」の第一稿は、「偶然性に関する抽象的で長い瞑想」であったらしく、それはサルトルが、1930年1月から18カ月の間の義務兵役に就き、余暇に書いた一連の著作のひとつであるエッセイ「真理伝説」に近かった。サルトルは、この期間に「樹木」と題された詩や、小説の一章、戯曲「エピメーテウス」などを書いた。除隊後に「真理伝説」をいくつかの出版社に持ち込んだものの、どこからも断られてしまう。
サルトルの内縁の妻、シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、主人公ロカンタンの発見に小説的な次元を与えること、探偵小説のなかで彼らが気に入っていたサスペンスを少しばかり物語に導入することを、サルトルに力説した。そしてサルトルは、1932年刊行のルイ=フェルディナン・セリーヌの長編小説「夜の果ての旅」の文体を手本にし、「真理伝説」で使っていた堅苦しい文体を捨てた。サルトルとボーヴォワールは、「話し言葉と同じくらい生き生きとしたエクリチュール(文章)を、セリーヌが作り出したと考え、セリーヌの文体を手本にした。
冒頭には、セリーヌの小説『教会』からの引用があるが、サルトルが引用したのは「彼は社会的に重要な人間ではない。正真正銘の一個人である」という一節。セリーヌは、サルトルやボーヴォワールを熱狂させ、実存主義にも影響を与えたフランスの作家。その次のページには、「カストールに捧ぐ」という献辞があるが、これはボーヴォワールの綽名。
1933年から34年にかけての一年間、サルトルはベルリンに留学し、そこで現象学を研究しながら、「偶然性に関する公開状」の第二稿を完成させた。また、当時のサルトルの愛読書は、フォークナー(アメリカ合衆国の小説家)、カフカ(プラハ生まれの小説家で、ドイツ語で書いた)、フッサール(ドイツの哲学者)であった。
1934年の秋から、サルトルは再びル・アーヴルで教壇に立つが、翌年の2月、メスカリンの注射を受けて幻覚症状を自ら体験しようとした。現代人との感覚とは違うのか、少しばかり驚いてしまう。メスカリンによる幻覚症状は、かなり長期間にわたって続く。日本では、メスカリンは法律上の麻薬に指定されている。
1936年、サルトルは「偶然性に関する公開状」をさらに書き直す。デュラー(ドイツのルネサンス期の画家、版画家、数学者)のエッチングの題を借りて「メランコリア(憂愁)」と改題もした。そしてガリマール書店に持ち込んだが、この時も採用されるには至らない。
翌年、再度売り込んだ結果、漸く出版されることが決定。その時、社主ガストン・ガリマールの意見により、『嘔吐』と改題されて刊行された。その年のゴンクール賞の候補作となるが、残念ながら数票の差でアンリ・トロワイヤの『蜘蛛』に敗れる。現在の文学史では、おそらく逆の評価といってもよいのだろう。
『嘔吐』の初期の版には、挟み込み広告がつけられていて、サルトル本人による内容の紹介がなされていた。サルトルの意図は、「形而上的真理と感情とを、文学的形態の下に表明すること」であった。
サルトル本人による内容の紹介を、かいつまんで述べると、次のようになる。
長い旅行をしたあとでアントワーヌ・ロカンタンは、ブーヴィルのホテルに居を定めた。そこでロカンタンは、18世紀の冒険家、ド・ロルボン氏に関する史学上の論文を作成している。ロカンタンはしばしば図書館に赴く。そこでは独学者でヒューマニストでもある友人が、アルファベット順に本を読みながら自分を教育している。夕方になると、ロカンタンは<鉄道員さんの店>というビストロへ行く。いつも同じ<Some of these days(いつか近いうちに)>という、ジャズのレコードを聴く。そして、ビストロの女主人と一緒に二階の寝室へ。
ロカンタンが愛しているアニーは、四年前から居場所が不明。彼女は<完璧な瞬間>が存在することを常に望んでいた。そのせいか、彼女は細かくて無駄な努力にたえず精根を枯らしていた。二人は別れた。
ド・ロルボン氏にしがみついていたロカンタンであったが、ほんとうの冒険が始まる。あらゆる感覚の変貌。表面上は静かだが恐ろしい。それが<嘔気>である。
アニーがロカンタンに手紙を寄越したので、再開しに行く。再開したアニーは、肥って絶望した鈍重な女になっていた。その後すぐに、ロカンタンはド・ロルボン侯爵に関する歴史上の調査研究を完成させることを止めて、ブーヴィルを去りパリへ戻ることを決意する。
ブーヴィルにおける最後の日、ロカンタンは親しくしていた独学者を見つけようとして、街中を駆け回ったが見つからない。そのあと、図書館に本を返しに行く。二時間ほど経つと独学者が入ってきた。ロカンタンは別れの挨拶をしたかったが、独学者はよそよそしい。実は会食で彼に悪い思い出を残していた。そして事件が起こる。独学者が図書館で醜聞を晒すことになるが、それはロカンタンが予感していたことであった。
その一時間後が最後の日記。パリに出発する前に、ロカンタンは<鉄道員さんの店>の女主人に別れの挨拶をしに行く。彼女はロカンタンが好きなレコード<Some of these days>をかける。その時、ロカンタンは物語を書くことに興味が湧いてきた。
日記には次のようなことが書かれている。「私はこの男(作曲家)についてなにかを知りたいと思う。(中略)それを知ったら面白かっただろう。(中略)もちろん、ヒューマニズムなどからではまったくない。それとは逆である。ただこれを作ったのが彼だからだ。私は別に彼と識合いになりたくはないし ―― それにもう死んでいるかもしれない。ただ彼に関する二、三の情報を得ること、そしてときどきこのレコードを聞きながら、彼のことを考えることができればそれでいいのだ」、と。さらに、「彼ら、作曲家と歌手とは、私にとって、いくらか死者のようであり、いくらか小説の主人公たちのようである」。そして、「歴史に関する論文なら書いたが ―― それでは話にならない。一冊の書物。一篇の小説」、と。
小説「嘔吐」には、サルトル本人の体験が鏤められている。ロカンタンが赤毛だったのは、共産主義者の同窓生が赤毛だったから。他の登場人物の何人かも、モデルになった人物がいる。描かれた場所が実在するなど、小説の細部において体験が活かされている。しかし、自分の体験を語るのがこの小説の目的ではない。ロカンタンという人物によって人間存在はなにかを追求することが、この小説の目的であった。「人間存在の根源的偶然性を示すには、このような小説形式を採用するしか方法はなかった」。
作者サルトル本人のこの小説に対する態度は微妙に変化した。第二次世界大戦後、サルトルは文学のアンガージュマン(社会参加)を提唱し、政治活動に傾斜する。1954年には、文学なんかろくでもないとボーヴォワールに放言した。1964年の自伝『言葉』において、『嘔吐』は文学という神経症に罹っていたときの産物に過ぎないと記す。だが、自伝『言葉』の刊行に際してのインタビューにおいては、次のように語っている。「神経症はエクリチュール(書く行為)のおかげで、私に幸福を与えてくれた……。(中略)私は飢餓で子どもが死んでいくのを見た。死んでいく子どもを前にして、『嘔吐』はなんの価値もない」、と。これが本心であると受け止めたい。
さらに次のような発言もある。「『嘔吐』のような虚構と、飢え死にする子どもを同一平面上に置こうとするのではなく、飢えている世界では文学にどんな意味があるのか、という質問を提出することが重大だった」、と。
1975年のインタビューでは、サルトルは冷静さを取り戻し、次のようなことを述べている。戦前、自分がしなければならないと思っていたのは書くことだった。政治的意見を持っていなかったし、エクリチュール(書く行為)を社会的行動として捉えていなかった。『嘔吐』は、<独りの人間>という理論の文学的到達点である。
著書のいずれが新しい世代によって再び取り上げられるのを望むか、という質問に対しては、「シチュアシオン」「聖ジュネ」「弁証法的理性批判」「悪魔と神」に続けて、次のようなことも述べている。「『嘔吐』こそ、文学的見地から言えば、自分が最善を尽くした作品だと考えている」、と。また、「マルクス主義者と呼ばれるよりは実存主義者と呼ばれるほうが自分には似つかわしい」とも。
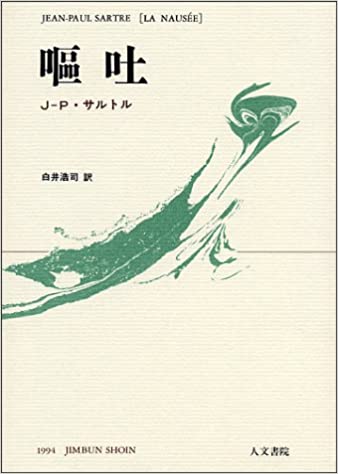
書誌情報
書名:嘔吐
著者:ジャン=ポール・サルトル
翻訳:白井浩司/新訳 鈴木道彦
出版:人文書院
発売年月:単行本 1994年1月/単行本(新訳) 2010年7月/電子書籍(新訳・Kindle版) 2021年7月
ページ数:単行本 312ページ/単行本(新訳) 340ページ
ジャンル:海外文学
Cコード:0097(外国文学小説)
紙書籍
電子書籍(Kindle版)


