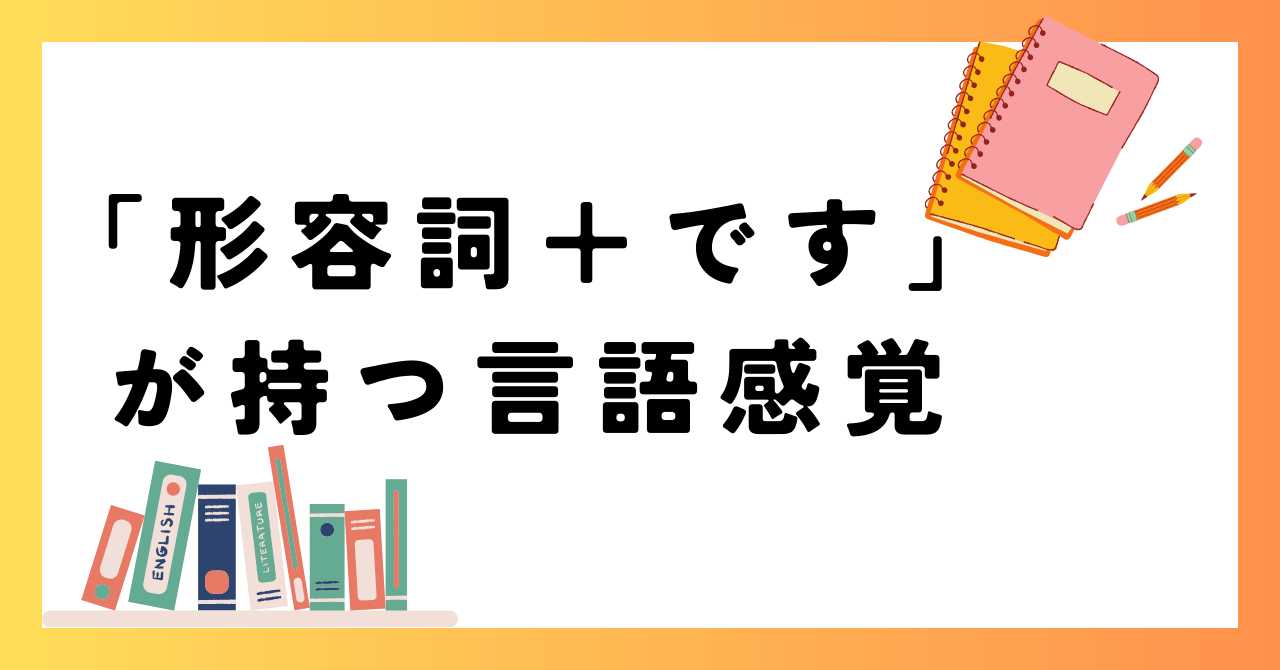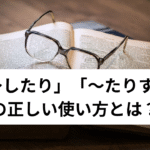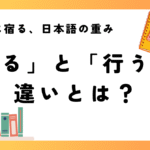「きれいです。」「楽しいです。」
そんな文末で締めくくられた文章に、あなたはどんな印象を抱くだろうか。
朗らかで親しみやすい響き。一方で、どこか物足りなさや、平板さを感じることはないだろうか。
話し言葉では当たり前のように口にする「〜です。」という語尾。しかし、それが文章の末尾に置かれたとき、言葉はふと、軽くなりすぎてしまうような気がする。
文体に敏感な書き手であればあるほど、その軽さに違和感を抱くだろう。けれど、それは本当に「誤り」なのだろうか。
本稿では、「形容詞+です」という、いまや日常語の一部と化した文末表現に目を向け、その〈軽さ〉の正体を探ってみたい。書き手としての感性を磨くためにも。
話し言葉のようなやさしさ――「〜です。」という響き
日本語における「です」は、丁寧語の一部である。相手への配慮や距離感の調整に使われる、いわば礼儀の道具だ。
「きれいです」「寒いです」「やさしいです」。こうした語尾は、現代の日常会話ではごく自然に耳にするものだ。とりわけ、話し相手が子どもであったり、親しい間柄であったりすれば、その柔らかさは心地よさへとつながっていく。
だが、書き言葉の世界ではどうだろうか。手紙、エッセイ、小説、評論。そこでは、語尾の選び方が文体を決定づける重要な要素となる。文章は、口に出して発する言葉とは異なり、紙面上で読み手と向き合う営みである。
ゆえに、言葉のひとつひとつが、読み手の心の中に独特の響きを残す。
「美しいです。」という文末。確かに間違ってはいない。けれど、その語尾にある種の「甘さ」や「無難さ」を感じ取る人も少なくないだろう。
書き言葉は、往々にして語尾の選択によって文の緊張感を生む。そこで「〜です。」が繰り返されると、文全体が平板に感じられることがあるのだ。
形容詞に「です」をつけることの意味――文法から見るゆらぎ
そもそも、形容詞とは単独で述語として成り立つ品詞である。「高い」「寒い」「やさしい」など、主語と直接結びつき、その状態や性質を述べることができる。
対して「です」は本来、名詞や形容動詞と結びつく補助的な言葉である。
たとえば、「静かです」「有名です」は、形容動詞に丁寧語がついた形であり、文法的にも自然だ。だが、「高いです」「寒いです」などの形容詞に「です」を添えるのは、もともと文法的な必然ではなかった。
それがいつしか、丁寧な印象を持たせるために、「形容詞+です」が使われるようになった。とくに教育の現場では、子どもに丁寧語を教える段階で「寒い→寒いです」「うれしい→うれしいです」といった形が定着している。
この用法が広がることによって、現代の話し言葉では「形容詞+です」がむしろスタンダードな形式として受け取られるようになった。
しかし、それが書き言葉にそのまま流入するとき、どこか文体上のちぐはぐさが残るのだ。
「稚拙に見える」と言われるのはなぜか
「この絵はきれいです。色がにぎやかです。そして楽しいです。」
こうした文章は、ある意味で明快でわかりやすい。だが、文芸作品やエッセイ、評論といった、ある程度文体の格調を求められる文脈では、あまり好まれない傾向にある。
その理由のひとつは、〈語尾の単調さ〉である。
文末というのは、文全体の印象を決定づける場所でもある。そこがすべて「〜です。」で統一されていると、読者は次第にリズムの平坦さに飽きを感じてしまう。
さらに、「〜です。」には、ある種の〈自己主張の弱さ〉がある。
「きれいだ」「きれいである」「きれいに感じられる」などの語尾は、書き手の視点や判断を明確に伝える力を持っている。
一方、「きれいです」という表現には、断定的な強さが希薄で、どこか受け身のような印象を与えることがある。
もちろん、これが一概に悪いとは言えない。だが、「書き手の言葉」としての芯を求められる場では、物足りなさや未熟さと取られる危険があるのだ。
文体の選択としての「〜です」――その場にふさわしい響きを
とはいえ、「形容詞+です」をすべて否定するのも、また短絡的だろう。
たとえば、ブログやウェブエッセイ、読者との距離感を重視した文体では、この「〜です。」の持つ柔らかさがむしろ大きな武器になる。
「うれしいです」「悲しいです」「安心しました」――こうした表現が、ある種の親密さや信頼感を生み出すことがある。書き手が自身の感情や印象を、丁寧に、けれどおおげさにならず伝えようとするとき、「〜です。」という語尾は有効なのだ。
問題は、それが〈無自覚に〉使われていないかどうかである。
「です」が繰り返されることにより、文のリズムが単調になっていないか。
その語尾が、本当に書き手の伝えたい語調・語感と一致しているのか。
文体というのは、文法以上に、感性と選択の問題である。
言葉の軽やかさと重みのあいだで
言葉は、書き手の呼吸を映す。
「形容詞+です」は、その響きのやさしさゆえに、読む者の心にふわりと入り込むことができる。
だがその一方で、言葉の輪郭を曖昧にし、印象を希薄にしてしまう危うさも孕んでいる。
だからこそ、書き手は言葉のリズムに対して、もう少しだけ敏感でありたい。
「きれいです。」で十分伝わると感じるなら、それでよい。
けれどもし、「きれいだ」「きれいである」「きれいに見える」といった選択肢が浮かんだなら、ぜひその手触りを比べてみてほしい。
たった一語の違いが、文章の質感をがらりと変えてしまう。それが日本語という言語の奥深さであり、書くことの愉しみなのだから。
文末とは、文の終わりではない。それは、読み手の中にことばを残していくための、静かな余韻である。