瀬戸賢一さんの著書『書くための文章読本』を紹介します。
文章の質を高めるには?日本語の文末表現とレトリックを学ぶ
『書くための文章読本』の著者は、レトリックや英語学を専門とする言語学者・瀬戸賢一さんです。
瀬戸賢一さんは、1951年京都府生まれ。著書に『メタファー思考』(講談社現代新書)、『日本語のレトリック』(岩波ジュニア新書)などがあります。『プログレッシブ英和中辞典[第五版]』(小学館)などの編集主幹を務められた方です。
レトリックは文学における大きなテーマのひとつ。
日本語の文末問題をメインテーマとし、レトリックの周辺を長年研究してきた立場から書かれた、視野を広げてくれる興味深い内容でした。また2019年刊行の本書に書かれていることは、新鮮な内容でした。
本書のメインテーマは「文末」。日本語の文末問題に焦点をあて、作家とはちがった視点で書かれた文章読本です。レトリックの周辺を長年研究してきた立場で、できるだけ明確な回答を心がけたと、あとがきで述べられています。
本書の技法を上手く取り入れると、単調で味わいの乏しい日本語の文末が、変化に富んだ文体に様変わりするはずです。レトリックの習得による効果は、文末から文章全体に広がります。様変わりする程度は、どこまで取り込むか次第でしょう。
本文の冒頭は、「デス調」と「デアル調」の選択についてです。これは、読者との距離感、内容の硬軟などと深く関係し、文章全体に影響を及ぼします。「デス・マス調」という言い方は、「デス」が相性のよい「マス」を引き寄せた結果です。また「デアル」は「ダ」との相性がいいので「ダ・デアル調」と呼ばれます。
ご存知のように「デス・マス調」は敬体(丁寧体)ともいわれるように、やさしい語りかけです。一方、「ダ・デアル調」は常体とも呼ばれ、受け手との距離をやや広くとり、あまり感情を交えない語り口といえるでしょう。
なお敬体と常体は、必ず統一しなければならないというわけではありません。
むしろ文章のなかで使い分けたほうがよいのです。その方が、優れて読みやすい文体になります。この事は、小説やエッセイ、ノンフィクションなどの文学作品に限らず、他の諸学を論じた本でもいえます。
敬体と常体を混交してよいことは、実際に出版された書籍を読めば明らかです。一流作家の文章を幅広く読んでいると、徐々に判ってくると思います。ただし、書く時のコツのようなものはあります。
敬体と常体をうまく書き交ぜるだけでも、単調で味わいの乏しい日本語の文末が、変化に富んだ文体に様変わりするはずです。
ポイントの一つは、敬体の「デス・マス調」には広く常体が入り込んでいるのに対して、逆のケースは稀だということです。常体の「ダ・デアル調」の中に敬体が混じる文章は、カギかっこ付きの会話文による直接話法は別として、話の地の文ではあまり見かけません。あるとすれば、段落の最後などにトーンを変えて、敬体で読者に語りかける場合などです。
ただし現代日本語で文章を書く際は、常体というくらいですから「ダ・デアル調」が基本と考えられます。その方が、簡潔に表現できるはずです。
接続要素に関しても、厳密なものではありませんが、敬体寄りの要素と常体寄りの要素があります。これも、読者との距離感、著者の内心などに結びつきながら、微妙に変化するのです。
日本語の二つの調子、常体と敬体において過去を表す場合、共通して文末に「た」を用います。「デス・マス調」が「でした」と「ました」という形で、「ダ・デアル調」は「だった」と「であった」です。よってどちらの調子を選んでも、過去の話をするときは、いつも「た」で終わってしまいます。
ふだん話すときは、過去や現在や未来のことをまぜて語ります。意識することは少ないでしょう。
しかし小説の場合は違います。一般論として、未来小説やSFを含めて、小説は過去形で書きます。これは、未来の出来事であっても、書き手の視点をさらにその先の未来に置くためです。もし現在形になっているなら、それは場面設定と考えられます。
いずれにしても、小説においては「た」が支配的です。そのため文末問題の影響を強く受けます。
かつて日本語には、「き」「けり」「ぬ」「つ」「たり」「り」といった、時の助動詞がありました。そのおかげで、あまり苦労せずに微妙なニュアンスを表現できました。しかし、いまさら過去の表現法を復活することはできません。よって、今の言葉を最大限に生かすしかないのです。
「デス・マス調」と「ダ・デアル調」を調整する。過去・完了の「た」に現在形を配合する。こういった手法により変化に富んだ文体に様変わりします。
実際の文章技法としては、前後の「デス・マス調」でサンドイッチするように、間に「ダ・デアル調」をはさみ込みます。この時のデアル調のセンテンスは具体例の列挙です。簡潔に並べられた常体文は、文章に律動感や躍動感を与えてくれます。
敬体から常体への切り替わりは、カメラのズームアップのように現場の被写体に寄っていくイメージです。
敬体へ戻るときは引きの映像。あるいはテレビの視聴中に中継が切り替わるイメージです。これには、文章中に描かれている対象物の主体性を高める効果があります。
そして敬体から常体へ切り替わる際、過去形から現在形への変化をうまく配合すると、さらに臨場感が増すはずです。現在形のほうが臨場感を増す。これは当然です。
描写対象の主体性に関して、少し違った角度で述べます。小説のセリフにおいて、「私」という一人称代名詞を言語化する場合と、省く場合とでは、現場からの距離がほんの少し変わります。
登場人物が「私」と発言すると、語り手が少し離れて眺めているような印象です。
省いて発言したほうが、現場に立っているという感覚が強まります。主語を省略すると、語り手が登場人物の視線をとることになり、主体性の高い表現を演出できるのです。
主体性の高い表現とは、視点の問題です。二人が向かい合って対話している場面をカメラが追うとします。この時、カメラはいくつかの角度から映せます。カメラが片方の人物の視点と完全に一致し、相手を真正面から見つめているなら、もっとも主体性の高い表現です。これは片方の人物の見え方そのものを表しています。
主体性の高低はカメラのアングルとクローズアップの度合いに相当します。小説の中では、主人公の知覚・認識という形で、主人公の視点から主体的に描写します。
三人称小説で主人公が作品の舞台に登場する場面では、カメラを少し引いて、主体性を少し下げる書き方がされているはずです。小説の視点は、カメラのアングルやクローズアップのように微妙に変化しているのです。
三人称小説において主人公の存在が視覚のみになっているときは、主体性が最高に高まっています。このような主体性の高まりは、ストーリー展開のさなかよりも、ふと立ち止まったり、物思いに沈んだりしているときに現れやすいようです。
小説の語り手には、知らせる・語る・感じるという3つの役割があります。この3つは境目がつねにはっきりしているわけではありません。「感じる」という中心カテゴリーがあり、周辺に「語る」があり、その周辺に「知らせる」があるというイメージです。
語り手は、導入部で知らせ、語りを展開し、視点を主人公と重ねることで感じたことを描写し、語りを終結させます。その際、語り手は主人公への微妙な出入りをしています。
語り手については、作者によって創造された、作中人物と考えたほうがよいでしょう。作者は、語り手とは異なり作品世界の外にいます。読者は作者がコントロールする語り手からストーリーを受け取っているのです。
とくに一人称小説の場合は混同されがちになるのかもしれません。主人公の「私」と語り手の「私」と作者の3人は、別々の立場にいます。
「知らせる」は物語の導入部や状況設定のことです。
たいていは冒頭におかれますが、場面転換があればその都度知らせることが必要です。ただし、場面設定をする前に、いきなり現場の出来事が語られることもあるでしょう。
「知らせる」ための場面では、カメラあるいは語り手は主人公からかなり引いています。その際は、全知全能の神の視点とはいわないまでも、半知半能をとっていると考えられます。話の内容によっては、一般知識を読者に与える必要があるのです。
小説では神の視点をとることは珍しくありません。全知視点は、歴史小説のような登場人物の多い大きな物語で使われてきた視点です。
神の視点では、語り手が作品の中を自由に移動でき、登場人物の心の中にも入っていきます。さらには、全知全能の神、万能の語り手となることもあります。テレビドラマなら、この方法が主流です。
主体性の調節を、作家が意図的に行っているかは別として、洗練された文章家の作品からは、彼らが文章技法として体得していることが推測されます。
文豪の作品は、無意識の域に達した芸術です。傑出した作家は、主体性を高めた作品も抑制した作品も書くことができます。彼らは文体を自在に操ることができるのです。
日本語の文末には、デス・マス調(敬体)とダ・デアル調(常体)の選択という大きな問題があります。けれども実際は、律儀に守られているわけではありません。もっとのびのびと書いても良いのです。
主体性という考えを導入すると、敬体と常体の混淆のさせ方と、基調の「た」に現在形を割り込ませるやり方を理解しやすくなります。これには視点や語りの構造も関係します。
さらに実践的に探ると、文章のなかに「対話」を取り入れるという感覚が有効です。
これは日本語の文末を豊かにする可能性を秘めています。モノローグ(独白)ではなくダイアローグ(対話)。自分の声に他者の声を重ねればよいのです。他者は読者でも、もうひとりの自分でもよく、問答法や引用の工夫などにより「対話」を取り入れます。
文章のなかに「対話」を取り入れる手法は、主体性の導入という文章技法の変奏です。
対話といえばやはり会話文です。
小説の会話からは、時代背景と対話者の人物像を想像できます。そして文末に登場人物の豊かな表情が示されていることに気付くはずです。
文芸作品などに使われる用語には、登場人物を推測できる役割語があります。時代物であったり、教授と助手であったり、お嬢様であったりと、登場人物が異なれば、語尾だけでなくセリフの言葉使いも違うので、すぐに誰のセリフか分かるのです。
コミックなどでは、語尾を特徴づけることでキャラクターを立てるやり方が頻繁に行われてきました。
また日本語には終助詞があります。「か、な、ぞ、とも、よ、ね、さ」などを文尾につけることで、ニュアンスが微妙に変化します。
そして動詞の活用語尾の利用もおすすめです。
文末に五段活用の終止形を使えば、簡単に文尾を変化させられます。
ダ・デアル調なら終止形が「る」で終わる動詞を避け、デス・マス調なら終止形が「す」で終わる動詞を避けながら、五段活用の終止形を使えばよいのです。
利用するのは五段活用の動詞です。上一段活用・下一段活用・カ行変格活用・サ行変格活用の終止形は、「る」です。
ただし五段活用の利用は、多用する方法ではありません。貴重なスパイスとしてとっておくべきでしょう。
日本語の語順では、動詞が来るのは最後です。修飾語句を加えるなどして目的語を膨らまそうとすれば、主語と動詞の距離が離れ、理解しにくい文章になるかもしれません。
文章において力点が置かれるのは文末です。文頭は主題を表す位置です。最後に焦点を絞り、情報の核を据えます。肯定か否定かの判断も、日本語では文末です。
文は何かについて、何かを述べるというのが標準的な型。何かを述べるときの中心部分は文尾に集中するのが普通です。
文末の工夫でまず考えられるのが、複合動詞や補助動詞の力を借りるという方法です。さらにオノマトペで動詞を強化する方法もあります。
他にも、名詞止め、あるいは体言止めという技法があります。
この技法に関しては、ぶっきらぼうだとか品が悪いという意見があるのも確かです。しかし、さまざまな分野において、文筆家としての評価も高い方が、名詞止めを行っています。
なお名詞止めというレトリックの歴史は長く、もともとは和歌の第五句を体言で言い切る技法でした。
名詞止めに限らず、形容詞止めと副詞止めも文章技法として使われています。副詞止めと倒置法の違いに関しては、前文の動詞にかかる副詞節だと判断すれば、副詞止めといえるでしょう。
「ない」というふうに否定で終わることも、文尾の変化につながります。「ない」はダ・デアル調ですが、デス・マス調であれば「ません」により変化をつけます。古風に「ぬ」や「ず」を使うのもあり得るでしょう。これらに終助詞をつけ加えると、バリエーションが増えます。
対話は言葉の本質です。書こうが話そうが、伝達は受け手がいることを前提とします。ときに自分自身のみが受け手であってもかまわないのです。
聞き手、あるいは読者を表現の中に取り込むことは、レトリカルな工夫の中心です。
文章のなかに対話的要素を取り込む範囲は、文末から文章全体に広がります。用法としては、問答法をはじめ、感嘆と祈願、読み手の名指し、相槌、倒置法、追加法、挿入法、省略法などが挙げられます。
表現のレトリックである問答法には、いくつかのパターンがあります。「著者が聞いて著者が答える」「自問自答」「読者が聞いて著者が答える」「修辞疑問」の4つです。問答法は、起伏に富んだ文章展開を可能にします。
著者が聞いて著者が答える、というパターンでは理想的な読者を頭に浮かべます。
この「自作自演」の問答法は、疑似的な対話の基本パターンです。言葉のキャッチボールがあり、議論に加わっている雰囲気の演出です。この場合、疑問文の文末は「か」が多くなります。「か」のほか、「だろう」や「の」などが考えられるでしょう。
自問自答のパターンでは、最初から自分に問います。
主に文章に弾みをつけ、メリハリをつけるために行います。「か」による問いを小さな楔として、ひとつ打ち込み、文章にリズムを与えます。
前述した、著者が聞いて著者が答える、というパターンでは、建前として読者に尋ねるポーズをとりました。ここが大きな違いといえるでしょう。
読者が聞いて著者が答える、というパターンでは、読者からの問いかけを想定して行います。
「他問自答」というちょっと風変わりなパターンで、一段演出のレベルが上がる技法です。
修辞疑問(レトリカル・クエスチョン)では、肯定と否定がひっくり返ります。
例えば「ではありませんか」という表現がこれです。「ではありません」が「か」を伴い疑問文になっていますが、伝える内容は平叙文の「です」に近く肯定的に解釈されます。
逆に「どこにあろうか」という表現が帰着するのは、「どこにもない」という否定的な意味です。
この問答法に「選択疑問」というパターンをつけ加えさせてください。
これは修辞疑問と重なる用法です。
文末が「AかBか」「Aかどうか」といった終わり方をします。
例えば「…であったのかどうか」は、「…であったのかどうか疑わしい」というニュアンスにとれるでしょう。
感嘆なら「なんと…だろうか」といった言い回し、祈願なら「…(ます)ように」という祈りの形があります。
読み手の名指しに関しては、「あなた」や「私たち」という単語を文中に持ち込めばよいのですが、かっちりした文章なのか、アットホームな感じにするのかなどで選ぶ単語が変わります。
倒置法はふつうの語順を逆転させる技法です。文末に焦点をあて強調するために行います。
これに近いものに追加法があります。
倒置法は正常な語順に戻せますが、追加法はできません。
例えば「もっとも…けれど」「…けれども」「…なので」「…だから」「…のように」などの文末表現が挙げられます。
追加法に関連するものとして挿入法があります。
もっともポピュラーなやり方が丸かっこで括る、あるいは二マス分のダーシーで前後に割り込む形です。読点だけで強引に割って入るというやり方も含まれます。
補足や弁明が本筋の目的ですが、陰の声を響かせるために入れることもあります。
省略の全般に触れようとすると、「私」などの人称代名詞の省略も含まれますが、大胆な省略は豊かな文末を生む手立てにもなり得ます。
話が変わりますが、本文中にひとの言葉を引用することがあります。
本書においては、引用について幅広く解釈しながら考えを深め、重要視しているようです。
引用は文章に起伏をつけて、彩りを与えてくれます。引用といっても、その広がりは相当です。その場合、欠かせぬ技法となり、文末とも関係します。広い意味での引用は、文章の本体そのものです。書き手は、引用の元となる発言なり思いなりを、自分の文章のなかに取り入れます。
引用には、直接引用と間接引用という2つの種類があります。そして文章技法上、より重要なのは間接引用です。書き手の関与をできるだけ抑えたのが直接引用であり、思い切って自分の言葉で解釈して取り込めば間接引用となります。
日本語の直接引用と間接引用の違いは、カギかっこのあるなしが大きな基準です。この場合、直接話法と間接話法への言い換えもできるでしょう。
ただし新聞などのジャーナリズムでは、カギかっこ付きでも一字一句正確な引き写しとはかぎりません。記者による判断を経た要約であることが多いのです。この場合は矛盾する表現ですが、カギかっこ付きでも間接引用ということになるでしょう。
間接引用のメリットは、自己流にアレンジできることです。
直接引用でもアレンジできますが、言葉を借りるのだから控えなければなりません。
多くの場合、直上の文が引用であれば、助詞の「と」が現れ、「言う」「考える」「思う」などの伝達動詞で受けます。これは引用文の根拠ともいえるでしょう。さらに丁寧に、引用の「と」と伝達動詞の間に主語を入ていれば、よりはっきりと伝わります。
ただしこの書き方だと間延びするかもしれません。
助詞の「と」・主語・伝達動詞のいずれか、もしくは全てを省略することで、簡潔で力強い文章が生まれることもあるのです。
伝達動詞などを省略したまま、その場の状況を述べることで、歯切れのよい文体が生まれます。
また伝達動詞の代わりに、しぐさを用いると味わいのある文章になるでしょう。
さらに「と」で終わらせる「と」止めもよく見かける手法です。
引用の「と」を伴う手法は、間接引用にも直接引用にも当てはまります。そして間接引用であれば、自分の言葉で好きなように語れます。しかし引用の手法は、引用の「と」を伴い、必要であれば主語や補助動詞をつけるというやり方に制約されるわけではありません。もっと自由な方法もあります。
ただしカギかっこの直接引用の連続は、単純なのでできそう見えても、地の文の支えがなく、なかなか難しい書き方です。
これは、小説をとばして、いきなり芝居の台本を書こうとするようなもので、お勧めできる手法ではありません。また、ほとんど文学作品などに限られる手法といえるでしょう。
しかしカギかっこがつかない引用を、地の文でふつうに書く方法もあります。
初級レベルは、書き手の心の呟きを、地の文のなかに流し込むという手法です。カギかっこ付きの直接引用でもよさそうですが、あえてかっこをはずします。
これを本書では自由直接引用としています。
直接引用のカギかっこをはずし、そのまま地の文に自由に挿入するイメージです。間接引用ではなく、あくまで直接引用の自由な使い回しと考えてください。
引用元は心のなかの発言または思考。自分の心でも、ひとの心でもよいのです。ひとの心の場合、あくまで推測の域ということになりますが、それでいいのです。これらを地の文に紛れ込ませれば、広い意味での引用です。
ひとの心に飛び込み、その内面から実況放送する。主体性が高まり、登場人物と一心同体になり、その思いを直接語る手法です。
このような主体的な引用技法は、もともと近代の文学が考えだしたものです。
例えば三人称小説の地の文に、「私は」で始まるセリフを自由直接引用の手法で流し込むことで力強さが発揮されます。
一人称で綴るエッセイにおいても、それまで読者と向き合っていたのを、自分に言い聞かせ、自身と向き合うために、自由直接引用で表現するこがあるのです。
自由直接引用にふさわしいのは、内心の言葉です。
机上で練ったような言い回しは、あまりふさわしくありません。
この辺はセンスを磨いていくしかないでしょう。
ただし話し言葉そのまま、思ったことそのまま書くのでは、芸がなさすぎです。
エッセイストは、体験に基づく文章であっても、その場で思ったり呟いたりした表現に机上で練った言い回しを加えています。
文章はあくまで装った表現です。
書誌情報|『書くための文章読本』
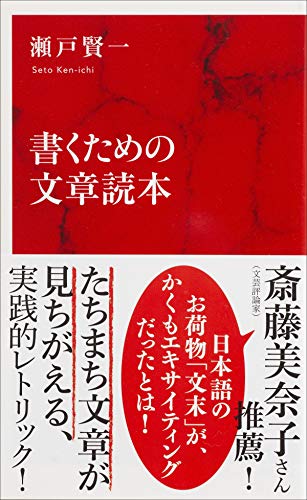
書誌事項
書名:書くための文章読本
著者:瀬戸賢一
出版社:集英社インターナショナル
発売年月:新書 2019年12月/電子書籍 2020年2月
ページ数:新書 224ページ
ジャンル:語学・教育
Cコード:C0281(日本語)


