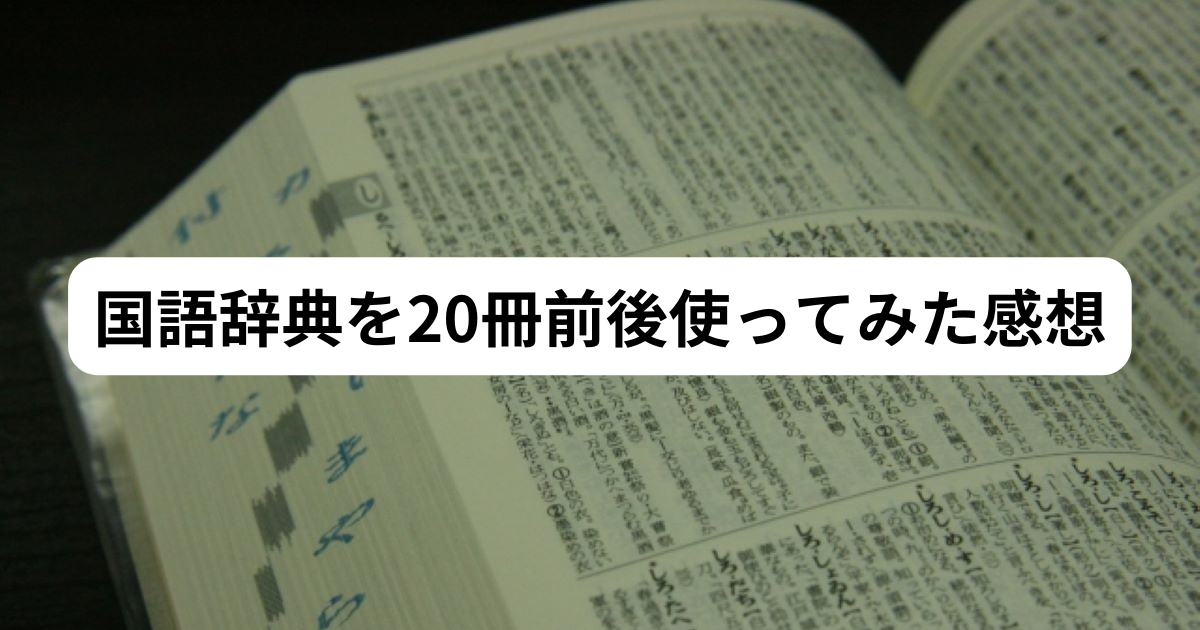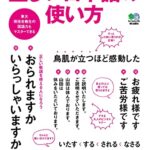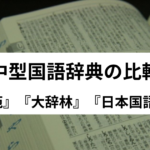小型国語辞典を、学生時代に購入したものも含めて20冊前後所有しています。国語辞典には特徴があるので、発行年度が新しい辞典を中心に、使用する辞典が徐々に固定し、使い分けもしています。
ただし、『精選版 日本国語大辞典』(小学館国語辞典編集部)、『大辞林 第二版』『大辞林 第三版』(松村明, 三省堂)、『広辞苑 第七版』(新村出, 岩波書店)といった中型国語辞典も所有しているので、通常はそちらを使用しています。『大辞林 第二版』は紙の辞典ですが、他の中型国語辞典はアプリや電子辞書です。
小型国語辞典に関しては、『ベネッセ表現読解国語辞典』(沖森卓也・中村幸弘, 2003年5月初版発行)や『てにをは辞典』(小内一, 三省堂, 2010年9月17日発行)などのように、中型国語辞典にはない特長があると利用機会が増えます。
『ベネッセ表現読解国語辞典』は、高校生から一般社会人が対象で、収録項目数は3万5千項目と少ないですが、書くことの手助けになります。また、何事も基本は大事です。辞典部・漢字部・機能語部・敬語表現部の四部構成で、言葉の特性に応じて、もっともわかりやすいスタイルで解説するというのが、方針のようです。収録項目数が少なくても、国語力を総合的に伸ばすのに役立ちます。国語の全体像を把握できる構成にし、主に高校生を対象にしているのかもしれませんが、他の国語辞典では得られない特長があります。
『ベネッセ表現読解国語辞典』は、文章を書く時に役に立つ辞書であり、記号化した言葉ではなく、文脈のなかでの使い分け、的確な表現が得られること、迷いなく表現を選べることなどが、本書の特徴です。文学からの引用が多いところも、自分にとってはしっくりとします。
ただし、漢字部・機能語部・敬語表現部に関しては、言葉の機能ごとに国語辞典一冊にまとめているのがよいのであって、それぞれについて深く学びたいなら、それぞれの専門書がよいでしょう。例えば、機能語部とは助詞・接続詞・助動詞・文末表現などのことですが、それぞれの専門書が数多く存在します。機能語部と敬語表現部に関しては、何度か目を通して頭の中を整理したあとは、利用機会が減るかもしれません。ただ、両者ともよくまとまっていますし、辞典部と漢字部の内容も含めて、所有する価値は大きいでしょう。
『ベネッセ表現読解国語辞典』のほか、『新潮現代国語辞典』(山田俊雄・築島裕・白藤禮幸・奥田勲, 新潮社, 2000年2月5日発行)や『日本語 語感の辞典』(中村明, 岩波書店, 2010年11月25日発行)、『角川必携国語辞典』(大野晋・田中章夫, 角川書店, 1995年10月27日初版発行)についてもいえることですが、解説文に散見する文学的な表現が自分にとってはしっくりくるのがよいと感じました。
標準的な小型国語辞典を使って紙の辞書を引きたい時に、最初に手に取る機会が多いのは『集英社国語辞典 第3版』(森岡健二・徳川宗賢・川端善明・中村明・星野晃一, 2012年12月)かもしれません。理由は単純で厚みがあり、情報量が多いからです。第3版では、収録項目数が9万5千で、2,160ページ。他の小型国語辞典に対して差を付けています。特に百科事典の要素が加わっているという印象を受けます。また、漢字字典の要素があり、文字を確かめたり意味を比較したり熟語を調べたりするのに役立ちそうです。
同じく情報量があるという理由で次に手に取ることが多いのは、『明鏡国語辞典 第二版』(北原保雄, 大修館書店, 2010年12月1日発行)です。小型国語辞典のページ数は1,600~1,800程度が多いようですが、第三版について述べると、1,992ページです。収録語数が約73,000語と標準的な分、基礎語や重要語の解説が詳細であると感じました。高校生向けですが、誤用や敬語がわかる、疑問に答えてくれるといった特徴が、実際に読むと納得できます。出版元の大修館書店は、高校国語の教科書を発行しています。
また、『新選国語辞典 第十版』(金田一京助・佐伯梅友・大石初太郎・野村雅昭・木村義之, 小学館, 2022年2月発行)は、1959年11月に初版刊行。少なくとも私が所有している辞書の中では、もっとも歴史があります。定期的に改訂されていることも、小型国語辞典にとって重要です。しかも、初版の編者の一人は、著名な言語学者の金田一京助氏。
出版社を比較すると、文学分野への貢献度が高いという理由で、新潮社をはじめ集英社や小学館に魅力を感じます。古典文学について言えば、岩波や角川も重要な存在です。角川は俳句についても貢献度が高い出版社ですが、俳句の嗜みは美しい日本語を学びたい方にとって価値ある言語芸術といえるでしょう。
文学好きとしては、文学的な教養と表現に優れている『新潮現代国語辞典』も推したいのですが、絶版になってしまったようです。改訂は平成12年(2000年)の第二版が最後になりました。私は『新潮現代国語辞典 第二版』を所有しており、貴重かもしれません。
小型国語辞典の中では、『新明解国語辞典 第七版』(山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・山田明雄・上野善道・井島正博・笹原宏之, 三省堂, 2012年1月10日発行)、『三省堂国語辞典 第七版』(見坊豪紀・市川孝・飛田良文・山崎誠・飯間浩明・塩田雄大, 2014年1月10日発行)、『岩波国語辞典 第七版新版』(西尾実・岩淵悦太郎・水谷静夫, 2011年11月18日発行)などを、所有している方が多いのではないでしょうか。この3冊は社会人が使用している小型国語辞典のシェアにおいて上位を占めています。
『三省堂国語辞典 第七版』の序文には「中学生から年配者に至る幅広い年齢層の人々に分かりやすく解説」するという基本姿勢が書かれています。『新選国語辞典 第十版』のキャッチフレーズは「中学生から社会人まで幅広く使える」です。似たようなフレーズですが、微妙に違います。
『新選国語辞典』の初版刊行は1959年11月ですが、『三省堂国語辞典』の初版発行が1960年12月10日、『岩波国語辞典』の初版発行が1963年4月10日、『新明解国語辞典』の初版発行が1972年1月24日。4冊とも歴史が長いだけでなく、定期的に改訂されてきました。国語辞典においては重要なことです。よって、社会人が小型国語辞典を一冊所有するなら、この4冊は候補に挙がるでしょう。
個人的には『新選国語辞典』を好んで使うようになりました。理由のひとつは、初版の編者の一人が、著名な言語学者の金田一京助氏であるからです。また、他の3冊が新語の収録に力を入れ過ぎている、あるいは用例を採取する際の媒体の選択が近年の世俗的なものが多いように感じたことも理由として挙げられます。『岩波国語辞典』は、どちらかというと保守的な国語辞典に分類されるかもしれませんが、『岩波国語辞典 第七版新版』を読んでいると、新語の採取を重視しており、用例主義的な傾向が強まってきていると感じました。
ただし、報道業界に近い言葉の使い分けをしているのは、『三省堂国語辞典』『新選国語辞典』『岩波国語辞典』の3冊です。対して、『集英社国語辞典』『新選国語辞典』『明鏡国語辞典』は、基礎語や重要語を中心に正しい日本語を理解するのに適していそうです。新語や近年の用例に振り回されず、誤用に対しては毅然とした態度で臨むという姿勢が感じられます。この違いをどう受け止めるかは、意見が分かれそうです。
国語辞典にも特徴があり、『三省堂国語辞典』と『明鏡国語辞典』は新語に強く、用例主義と言われています。『明鏡国語辞典』のほうが、『三省堂国語辞典』よりも厚みがある分、説明が充実しています。『明鏡国語辞典』は誤用についても詳しいのが特徴です。『三省堂国語辞典 第七版』の収録語数が約82,000語であるのに対して、『明鏡国語辞典 第三版』は約73,000語ですから、必然的に新語の収録数は『三省堂国語辞典 』のほうが多くなるといえるでしょう。
『新明解国語辞典』は解釈の国語辞典として人気があります。『新明解国語辞典』と『三省堂国語辞典』は出版社が同じ三省堂ですが、二つの辞典にはそれぞれ異なる特徴があります。それが辞典の付加価値を生み、二つの辞典を出版する理由にもなっているのです。もちろん編者が異なることも、大きな違いと言えるでしょう。
『岩波国語辞典』も、普及している国語辞典の一つです。この辞典は、規範主義的な国語辞典と言われてきました。『岩波国語辞典』を使っていると、『岩波国語辞典』だからこその気付きを得られることもあり、疑問が解決することもあります。
辞書の冒頭の「第七版刊行に際して」を読むと次のようなことが書かれています。「初版は高校で習う程度の古典作品の事を念頭において、現代語・古語両用の辞書として出発した。しかし古語項目は第五版から涙を飲んで削った」、と。
また、「はじめに」においては、「現代の、話し、聞き、読み、書く上で必要な語を収め、それらの意味・用法を明らかにしようとした」「現代人の生活に必要なものはほとんど収めているはずである」、と書かれています。
現代生活に必要なものという観点から厳正することが、第一の特色。第二の特色は漢字の働きを明確にすること、第三の特色は一語一語の基本的な意味を解明すること、第四の特色は漢字による表記を実際の文章においてそのように書く習慣のあったものに限ったこと。よって、読むためにも、書くためにも、参考になるはずとのこと。第四の特色について補足すると「現在普通行われている意味・用法を解説した上で、以前行われた用法にも触れるようにした、とも書かれています。
『岩波国語辞典』は、日本語の中でも最も基礎的な語と思われるものに多くの分量をさくという方針です。漢語や和語などを調べたいときも、『岩波国語辞典』が良いかもしれません。ただ、歴史のある言葉だと、古語辞典を使うという方法もお勧めです。私は『岩波古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎, 岩波書店, 1990年2月8日発行)を使っています。
他には、『学研現代新国語辞典 改訂第三版』(金田一春彦, 2002年4月1日発行)、『角川必携国語辞典』(大野晋・田中章夫, 1995年10月27日初版発行)、『旺文社国語辞典 改訂新版』(松村明・山口明穂・和田利政, 1986年10月20日発行)なども所有しています。これ等の辞典も、状況によって使用頻度が増えます。所有している『旺文社国語辞典 改訂新版』は発行年度がもっとも古く、当時の言語感覚などを知るのに、役に立つことがあります。
『旺文社国語辞典 改訂新版』の編者、松村明氏は『大辞林』の編纂者として知られている方。『学研現代新国語辞典 改訂第三版』の編者、金田一春彦氏の父は京助氏。『角川必携国語辞典』の編者、大野晋氏もまた有名な国語学者です。
『角川必携国語辞典』は高校生から一般社会人が対象ですが、どちらかというと高校生向きかもしれません。百科事典の要素を加え、漢字の意味と書き順も記載されています。他にも漢和辞典の要素を加えた小型国語辞典はありますが、書き順を省くことが多いようです。ただし、初版発行が1995年10月で、その後の改訂は行われていません。
『角川必携国語辞典』の冒頭には、「この辞典を使う皆さんへ」と題した編者・大野晋氏による序文があります。高校生を主な対象として書いた序文のようです。この序文は、ノーベル賞作家・大江健三郎氏が、大きな国語辞典をがさがさになるまで使って、3冊も買いかえたというエピソードで締め括っています。大野晋氏は、1995年8月に書いたこの序文の中で、辞書がぼろぼろになるまで使いこんでいただきたい、と述べています。
類語国語辞典も一冊手元にあったほうがよいでしょう。私は 角川書店の『類語国語辞典』(大野晋・浜西正人, 角川書店, 1985年1月初版発行)および『角川類語新辞典』(大野晋・浜西正人, 角川書店, 1981年1月初版発行)を使っています。『類語国語辞典』は『角川類語新辞典』の小型版。サイズについては、もちろん紙の辞典の話ですが、私が所有しているのは『類語国語辞典』が紙の辞典で、『角川類語新辞典』が電子辞典です。類語国語辞典に関しては、紙のほうが断然使いやすく感じます。
特定の事柄を専門とする国語辞典には、『日本語 語感の辞典』(中村明, 岩波書店, 2010年11月25日発行)、『基礎日本語辞典』(森田良行, 角川書店, 1989年6月10日初版発行)、『てにをは辞典』(小内一, 三省堂, 2010年9月17日発行)などがあります。
『日本語 語感の辞典』は、漢字の使い分けや類義語の違いを含めて、言葉の微妙なニュアンスを整理して簡潔にまとめているところがよいと感じました。ただし、読むことを楽しめるという魅力がある一方、ニュアンスに特化しているため、使い方を工夫する必要があります。収録されている語句が限定的であり、辞書を利用する機会は限られるでしょう。
国語辞典には『日本国語大辞典』(小学館)のように、総項目数が50万を超え、全13巻からなる大型辞典があります。中型国語辞典には、『精選版 日本国語大辞典』(小学館)、『広辞苑』(岩波書店)、『大辞林』(三省堂)、『大辞泉』(小学館)があります。
私は大学時代に紙の『大辞林 第二版』(三省堂, 1995年11月3日発行)を使っていました。現在は、iPadとiPhoneにアプリをインストールし『精選版 日本国語大辞典』と『広辞苑 第七版』と『大辞林 第三版』を使っています。
また、CASIOの電子辞書「XD-SX6500」を所有しているので、国語系では『広辞苑 第七版』や『明鏡国語辞典 第二版』のほか、漢和辞典や類語辞典やカタカナ語辞典や古語辞典など多数利用できます。その他では、生活関連のコンテンツとして『日本大百科全書(ニッポニカ)』や『ブリタニカ国際大百科事典』、『百科事典マイメディア』、『日本歴史大事典』などを利用できます。加えて、学習関連のコンテンツとして『山川 日本史小辞典』『山川 世界史小辞典』なども重宝しています。この電子辞書だけでも事足りるかもしれません。
それでも、小型国語辞典を読み比べることを楽しんでいます。調べるというより読むという行為になると紙の辞書のほうが落ち着きます。
私は国語辞典が好きで言葉を調べるのが好きです。また、文章を書くことも好きであり、仕事も文筆業です。よって、日常的にこれらの国語辞典を引いています。
それぞれの小型国語辞典にはそれぞれの良さがあります。
出版社を比較すると、文学分野への貢献度が高いという理由で、新潮社をはじめ集英社や小学館には魅力を感じます。古典文学について言えば、岩波や角川も重要な存在です。角川は俳句についても貢献度が高い出版社であり、俳句の嗜みは美しい日本語を学びたい方にとって価値ある言語芸術といえるでしょう。
また、高等学校の国語教科書に関しては、「現代の国語」「言語文化」「論理国語」「文学国語」「古典探求」に三省堂と大修館書店が名を連ねています。大修館書店は「国語表現」「現代文A」「現代文B」「古典A」「古典B」の教科書も発行しています。
中学校の国語の教科書については、三省堂が発行者のなかの一社です。
小型国語辞典は、各出版社から様々な辞典が発行されていて、人によって好みや相性が変わるかもしれません。国語辞典を比較するために、改訂年度の近い社会人向けの国語辞典で新語やカタカナ語を引くと、辞書ごとに微妙にニュアンスが変化します。
例年、社会人向けの国語辞典では、売り上げ上位を『新明解国語辞典』『三省堂国語辞典』『岩波国語辞典』『新選国語辞典』などが占めているようです。この4冊には国語辞典の歴史があり、ブランドとして定着しています。ただし、社会人向けというよりも、現代の日常生活に必要な小型国語辞典、と言い換えるべきかもしれません。年配者や高齢者がテレビ番組を見ていて、分からない言葉が使われていたとして、小型国語辞典を使用する場合、この中の版の新しい一冊を手元に置くことが適切かもしれません。
上記4冊のほかは、『集英社国語辞典』も、社会人向けの小型国語辞典として知名度が向上しているようです。こちらは、収録語数が多く、百科事典的な要素が加わる国語辞典です。
小型国語辞典を見比べてみると、出版社や編者によって特徴があり、結構、違いがあります。調べる用字用語や目的に応じて使い分けられるように、数冊の国語辞典を所有するのが好ましいのかもしれません。
文章を書く仕事をしている方はもちろん、社会人なら数冊の国語辞典を所有して使い分けるべきでしょう。
▶関連リンク・おすすめ記事