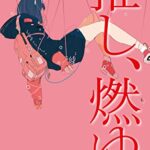綾辻行人さんの代表作『十角館の殺人』は、日本ミステリ史に残る傑作として、今なお多くの読者を惹きつけてやまない作品です。本記事では、物語の構造や登場人物の描写、そして読者を驚かせる仕掛けについて、多角的に掘り下げながら、本作の魅力と本格ミステリとしての完成度を考察します。
本格ミステリの到達点――『十角館の殺人』がなぜこれほど愛されるのか
綾辻行人さんの小説『十角館の殺人』を読んだ。
冒頭、復讐の幕開けを予感させるプロローグに、いきなり引き込まれる。わずか数ページを読んだだけで、綾辻の筆致がただものではないことが伝わってくる。これからどんな物語が始まるのか――自然と期待が高まる。
「彼」、つまり殺人を犯す人物はいったい誰なのか。読者は、その問いを胸にページをめくることになる。巧妙に仕掛けられた“叙述トリック”が、物語の中核にひそんでいる。
プロローグは、ひとりの人物が小さな透明なガラス壜を海へと投げ入れる場面で終わる。その壜の中には、びっしりと書かれた紙片――殺人計画の詳細が封じられている。まるで懺悔のような手紙。あるいは、神に委ねる「最後の審判」かもしれない。しかし、どんなに正当化しようと、復讐はやはり犯罪だ。彼はその罪と、良心の呵責に耐えられるのだろうか。
この印象的なプロローグの場面は、本作のラスト――エピローグへと見事につながっていく。
第1章では、大学の推理小説研究会の学生たちが登場し、「これは本格ミステリを書くための物語なのだ」と宣言するかのような会話が交わされる。社会派ではなく、トリックと論理を重視した“本格”であることが、作品の冒頭から明確に打ち出される。
『十角館の殺人』は、そんな本格ミステリを愛する読者のために書かれたような小説だ。発表は1987年。刊行からすでに数十年を経た今でも、多くのファンやミステリ作家たちから熱い支持を集めている。
もし、ミステリの醍醐味を味わいたいなら、本作は間違いなくその入り口になる一冊だ。現代の物語世界に、探偵のような存在が登場し、読者を驚かせる“大トリック”が仕掛けられている。今なお語り継がれる理由が、読めばきっとわかるはずだ。
孤島×推理=本格ミステリの極致 ― 『十角館の殺人』の構成美
一行で世界が反転する ― 本作が“伝説”と呼ばれる理由
本作の舞台となるのは、「十角館」と名付けられた奇妙な建築物が建つ孤島――角島。大学の推理小説研究会に所属する学生たちが、この無人島に合宿として集まり、やがて連続殺人事件に巻き込まれていく。登場人物たちは、それぞれ名探偵や怪奇作家にちなんだ“ペンネーム”で呼び合い、現実からやや切り離された“遊戯的空間”が構築されている。これは、本格ミステリにおける「密室」や「クローズド・サークル」の伝統を見事に踏襲した設定だ。
一方で、本土では別の人物が動き出す。過去にこの島で起きた“ある事件”の真相を探るうちに、十角館の現在の惨劇と過去の悲劇とが、やがて一本の線でつながっていく。読者は、二重構造の物語を行き来しながら、パズルのピースを少しずつはめ込む感覚を味わうことになる。
そして、何より本作を特別な一冊にしているのが、ある一行によって読者の視界が反転する瞬間――“叙述トリック”の衝撃だ。ネタバレを避けるため詳細は書かないが、この瞬間は日本ミステリ史に残る一撃であり、多くの読者が「してやられた」と笑い、「もう一度最初から読み直したくなる」と語る所以でもある。
『十角館の殺人』は、綾辻行人さんがデビュー作にして達成した偉業であり、のちに“新本格ミステリ”という流れを生み出す原点となった一冊でもある。後続の作家たち――例えば有栖川有栖さん、法月綸太郎さん、我孫子武丸さんなど――に大きな影響を与え、日本ミステリの地図を塗り替えた。
綾辻行人さんはその後も「館シリーズ」を続けていくが、『十角館』はその幕開けにふさわしい、完成度とインパクトを兼ね備えた作品だ。本格ミステリというジャンルの持つ純粋な面白さ――トリック、ロジック、驚き、そして知的遊戯――をこれほど鮮やかに提示した作品は、そう多くない。
たとえ普段ミステリを読まない人でも、この一冊を手に取れば、「物語に仕掛けがある」ことの面白さをきっと実感できるだろう。そしてその先には、より深く、より複雑で豊かな“館”の物語が、待っている。
まとめ――本格ミステリの魅力が詰まった一冊
叙述トリックの妙、密室の緊張感、そして過去と現在が交錯する構成――『十角館の殺人』は、本格ミステリの魅力が凝縮された一冊です。未読の方にはぜひ、あの衝撃の一行を体験してほしい。そして、すでに読んだことのある方にも、再読のたびに新たな発見があるはずです。
書誌情報|『十角館の殺人』
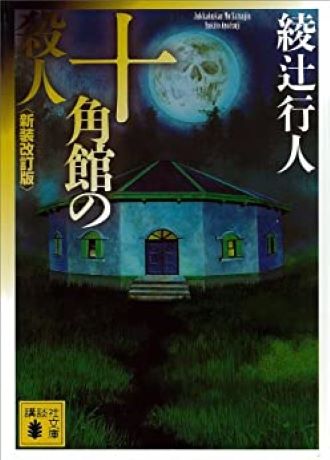
書誌事項
書名:十角館の殺人
著者:綾辻行人
出版社:講談社
発売年月:単行本 1987年9月(講談社ノベルス)/文庫本 1991年9月/文庫本新装改訂版 2007年10月/電子書籍 2007年10月
ページ数:文庫本新装改訂版 512ページ
紙書籍
電子書籍
補足情報
『十角館の殺人』は、綾辻行人さんのデビュー作。刊行予定が固まったあとにシリーズ化を思いついたとのこと。第4作で完結するつもりが、ある時点で続行を決め、完結予定を全10作までに改めたと述べている。館シリーズは長編作品であり、第7作の『暗黒館の殺人』は、新書が上下二分冊、文庫化のさいは四分冊に。
刊行の順番は『十角館の殺人』『水車館の殺人』『迷路館の殺人』『人形館の殺人』『時計館の殺人』『黒猫館の殺人』『暗黒館の殺人』『びっくり館の殺人』『奇面館の殺人』。つまり2021年2月現在、残すところあと一作。第9作『奇面館の殺人』が講談社ノベルスから刊行されたのが2012年1月。少し間隔が空いていますね。
なお講談社ノベルスは、主に推理小説を扱い、軽装の新書判で発行する講談社の小説レーベル。
『十角館の殺人』に関しては、講談社ノベルスと講談社文庫のほか、2017年に講談社から「限定愛蔵版」が、外箱・付録付きのハードカバーで発売されている。「限定愛蔵版」の付録冊子「SPECIAL BOOKLET」には、綾辻行人さんが書いた「三十年目の想い —— あとがきに代えて —— 」及び、著名作家らの「私の『十角館』 —— 33名によるエッセイ —— 」が収録されている。