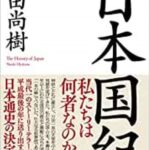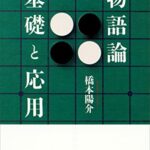藤吉豊さんと小川真理子さんの共著『「文章術のベストセラー100冊」の ポイントを1冊にまとめてみた。』を紹介します。
文章術の本についての案内書がAmazonで売れていたので私も購入しました。レビューを書いている人が多く、売り上げも比例していると推測できます。評価もまずまずでした。タイトルと評判の信憑性を分析したくなり、Kindle版を購入しました。
なぜこの本を手に取ったのか ― 購入のきっかけと期待感
私はAmazonで本を購入することが多く、文章術関連の本を購入することも多い。文章術の本に関しては、自分が目指すジャンルの著者や、好きな作家が書いた本、あるいは課題を解決できそうな本を選ぶのが普通かもしれない。
本書に関しては、タイトルに惹かれた。100冊も読み込んでいるなら、目から鱗が落ちる話も期待できるのでは、と思った。
本書の著者である藤吉豊さんと小川真理子さんは、現役ライター。お二人は、約30年にわたる出版の現場でのキャリアをお持ちだ。そして株式会社文道を設立された。ライター育成のセミナーなどを開催されているので、期待感は増す。
購入する時点ではAmazonレビューが999個あり、星4.1と、まずまずの評価であった。Kindle版の無料サンプルで、冒頭の内容や目次などを確認したら面白そうであった。
100冊の知見を1冊に凝縮 ― 本書の構成と特徴
文章術の本は、作家やジャーナリスト、ライターらが書くことが多い。また国語学者が書いた本になると、論理的で専門性が高くなり、本の雰囲気も変わる。
ライターやコピーライターの書いた本は、内容がやさしいことが多い。本書もそういう印象の本。やさしい文章術の本の中でも、やさしく読みやすく書かれていると感じた。すらすらと読み進められたので、ほぼ一日で読み終えた。
本書は、文章術の名著「100冊」のエッセンスや書き方のコツなどを1冊にまとめたものである。文章のプロが大切にしているルールから順に、身につけてもらう、というコンセプトに従っている。
著者のお二人が、名著100冊を読み込み、共通のノウハウを洗い出し、ランキング化している。Part.1がランキング1位から7位で、Part.2が8位から20位、Part.3が21位から40位、という構成である。
いくら客観的に書いたとしても、文章術の本なので著者の個性がでるのではと思った。しかし巻末の、「文ハ、是レ、道ナリ」と題した「おわりに」において、藤吉豊さんは次のように述べている。
「藤吉と小川が実践している書き方」にはほとんど触れていません。著者の色を出さず、第三者の立場で、客観的に、粛々と、「書き方のコツをランキング化する」ことにこだわった(引用)
もう一人の著者である小川真理子さんは、「おわりがはじまり。さあ、書き始めよう」と題して、自身が文章を書くときに大切にしていることを巻末の「おわりに」で語っている。
40項目の中でもとくに効果のある文章上達の方法は何かと聞かれたら、答えは「とにかく書く、たくさん書く(15位)」であると仰っている。
文章術の本を読み込んだ筆者が感じた効果と気づき
1位の見出しは「文章はシンプルに」である。ポイントは3つ。「余計な言葉はとにかく削って、簡潔に」「1文の長さの目安は60文字以内」「ワンセンテンス・ワンメッセージ」である。確かに文章術の本に書かれていることが多い。
私が今書いている文章やこのブログは、本書のセオリーにすべて即しているわけではない。意識しつつも文章が長くなることもある。依頼された仕事ほど意識しない。推敲の時間を大幅に削ってしまう。
もちろん、悪文・乱文を公開するつもりはない。
言い訳するつもりではないが、これまでの読書習慣の影響があるのかもしれない。子どもの頃から、大学生、社会人と大人になっていく過程で、小説を読む機会が多かった。古典も現代の作品もたくさん読んできた。それらの影響かもしれない。現在でも、読書は小説が多い。
少し長いかなと感じる記事でも、意味が通じるならそのままにしている。そのような時は、納品記事でも指摘されない。レベルの低い話になってしまうが、書き手と読み手の相性もあると思う。
100冊の中には、谷崎潤一郎の「文章読本」もある。谷崎作品は1文が長いことが多い。他の文章術の本で、プロのような書き方は難しいので、基本を大切にすべきとの記載を見たことがある。身の丈にあった書き方をする必要はあるだろう。
14位は段落についてである。ポイントが3つ書かれている。内容の切れ目と5~6行目の2つに関しては、小学校の国語の授業でも習うこと。
1行を40文字と考えての記述のようだ。単行本などはその程度であろう。それらを文章のプロの立場で解説している。
そして残りの1つが、ブログやSNSの場合。2~3行で改行と書かれている。
この箇所は、ブロガーが書いた本を参考にしている。note公式アカウントの記事を例にして、スマートフォンで見ると、2〜3行で空白行があるとも、書かれている。
本書では触れていないが、HTMLでは段落を<p>~</p>で囲む。すると改行が行われ、空白行が設定される。また、改行だけしたいときは、<br />を使う。
Googleの解析ツールで分析すると、スマートフォンで閲覧する方が圧倒的に多い。そのため、このような話の流れになるのかもしれない。ウェブ記事の場合、スマホでの閲覧を優先することになるのだろう。
著者は、見やすさの観点から必要であり、書籍や雑誌とは違うことを覚えておきましょう、とまとめている。付け加えると、メディアが違っても異なるであろう。
私も、クラウドソーシングで受注した案件などで、このような書き方を依頼されることがある。もちろん、そういう依頼であれば、そのように書いている。
ただ、ウェブ記事の場合、読者が使うコンピュータ端末の違いで行数は変わる。クライアントからの依頼は、2〜3行ではなく2〜3文である。また、ウェブやSNSでは1字下げしないこともある、と書かれているが、この場合は1字下げしないのが一般的であろう。1字下げするなら、2~3行で改行という書き方はしない。
個人的には、ウェブ記事のこういう書き方には、なかなか馴染まない。スマホで表示するのに、パソコンで書いているということもある。
また、話のまとまりや時間的な流れの変化という、根本的な文章作法に反する。改行が多すぎると、文章のまとまりが分かりにくい気がする。
著者は、名著のランキング形式として客観的にまとめ、お二人が実践している書き方にはほとんど触れていないと述べている。本音としてはどう思っているのかお聞きしたい。コーポレートサイトを拝見すると、実践されているようだ。センスがよいと思った。
巻末には付録として、添削の実例が載っている。その中に、「ブログやSNS、短いコラム等の原稿」とい実例がある。
それを見ると、見出しに配慮した文章になっていた。改行の際の1字下げをしている。段落と段落の間に、空白行は入れていない。
本書には、「見た目」の重要性についても書かれている。しかも3位である。ポイントは、余白・ひらがなと漢字のバランス・文章のリズムの3つ。広く知られていることである。
メールやSNS、ブログ、プレゼンテーション資料などは、書いたものがそのまま他人の目に触れる。書籍や雑誌などの場合と違い、レイアウトなどの「見た目」を整える能力も必要とされる。
話が少し変わるが、私はアメーバブログからはてなブログへ引っ越してきた。バックアップデータをインポートしたら、見た目が悪くなり大幅な修正が必要であった。はてなブログのテーマを替えたら、体裁は様変わりする。
13位は句読点。8つのルールおよびリズム・呼吸の、2つのポイントを挙げている。8つのルールの1つとして、引用の「と」の前に読点を打つ、という記述があった。これは、私も以前から実践していることだ。
だが、結果を示す「と」については触れていない。結果を示す場合は、「と」の後ろに読点を打つ。他の7つの内の1つに含めたのか、不要と考えたのかは分からない。
Part.3以降では、文章のプロでも意見が分かれるような内容が多かった。コピーライター、ジャーナリスト、作家などの違いを抜きにしての話である。
26位は同じ言葉の重複を避けることについて。理由は稚拙であるから。私も、その通りだと思う。
クラウドソーシングで受注した案件で、キーワードだからという理由でわざわざ重複させる依頼があった。SEOに関しては、ユーザービリティ(有用性、使い勝手)などに力を入れるべきであろう。最近はそのような方向へ進んでいるはずだ。
28位の見出しは、「日頃から内面を豊かに耕す」。人生観の話も出てきた。こういう話をされると、どうすればよいのか困ってしまう方もいるかもしれない。たとえば小説を読む作家を選ぶ際は、作家の人間性なども見ることになる。
売れているから、人気作家だからという理由で買うこともある。文学賞を受けた作品なので読むこともある。だが、評価されるまでに、作家は人間性なども見られている。書いた作品には思想が反映される。
名文から学ぶ話の時に、思想に共感できる作家、好きな作家の文章を見つけるという話があった。これに通じる話だと思う。
文章の書き方の本には、技術以上に内容や情報が大切という話がよく出てくる。本書では、それ以上に書き手の内面が大切であると強調しているように感じた。
6割が人生観で、残りの4割が情報とテクニック、という記述があった。文章の良し悪しを決めるのは、テクニックや情報以上に、書き手の「人生観」とのこと。結局は内面の深さがものをいうとも。悪文・乱文の解消には大切な考えであろう。素直に共感した。
10位、20位、32位は、名文から学ぶ話であった。本書における名文の定義に関しては、自分が良いと思った文章とのこと。そういった本を選んで、学ぶことを文章のプロはすすめている。
誰かが名文と評しているからではなく、自分が手本にしたいと思える作品を素直に選べばよいのだ。プロの多くも、そのようにしてきたのであろう。
ただ興をそぐが、文章は才能という意見もある。また、この段階でプロの文章を真似るのは至難の業。本書では、自分にとっての名文が見つかったら、繰り返し読んだり、書き写したり、真似たりすることをすすめている。
ただし、好きな文章に出会うためには、たくさんの文章を読む必要がある。文章の上達には、たくさんの本を読んだほうがよいという話にもつながる。いろいろな作家の文章に触れることも、文章力向上のための手段だ。
本書はどんな人におすすめか ― 要点のまとめと読後のヒント
文章術の本に興味があるなら、本書は最初の一冊としておすすめできる。どの本がいいのか分からない方にも、適しているだろう。私のように興味本位で購入する方もいるかもしれない。文書術の名著100冊を紹介していることにも価値がある。
ただし本書だけでは、他人の文章を評価したり指導したりできるレベルまでは達しない。自分の文章を磨くための参考にするべき本である。
内容がやさしく、読みやすいことは、本書の魅力になっている。本書が人気なのも頷ける。Part.1に書かれている内容をありきたりに感じるような方でも、中盤あたりからは参考になりそうだ。
だが、少し難解な本を読むことで鍛えられ、文章力が向上することも事実。本書で参考にした本は、まとめて紹介されているので、何冊か読んでみると良い。
100冊の中には、私が所有している本が何冊もあった。文章術の本を何冊も読んでいるので、以前にも読んだことがある話も度々登場した。そういう時は復習のつもりで読んだ。
本書は、谷崎潤一郎の「文章読本」や本田勝一さんの「日本語の作文技術」などに比べると、内容も文章もかなりやさしい。本書では、文体が古くて読みづらい本に挑戦する意義にも触れている。
言語学の専門書でも文章術の本でも、ある程度はテーマを絞っていることが多い。本来はそうすべきなのかもしれない。
本書は、多くの本の中から、重要と思われる箇所を抜粋しているので、得した気分になる。興味を持てる内容であり、面白かったので、ほぼ一日で読了した。文章術を磨きたい方の役に立つ本であることは確かだ。
書誌情報|『「文章術のベストセラー100冊」の ポイントを1冊にまとめてみた。』
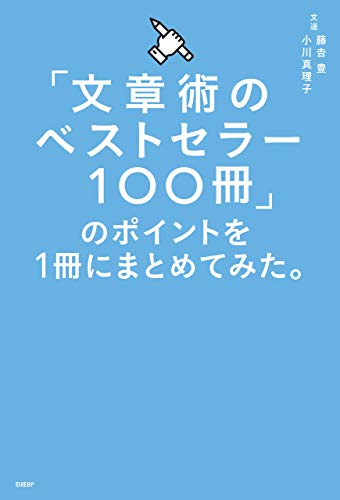
書誌事項
書名:「文章術のベストセラー100冊」の ポイントを1冊にまとめてみた。
著者:藤吉豊・小川真理子
出版社:日経BP
発売年月:単行本 2021年1月/電子書籍 2021年1月
ページ数:単行本 224ページ
Cコード:C0030(社会科学総記)
※藤吉さんの苗字の「よし」の字は異体字で、上の部分が「士」ではなく「土」ですが、変換できなかったので、常用漢字「吉」を使わせていただきました。