ふくだたみこ氏の著書『SEOに強い Webライティング 売れる書き方の成功法則64』(ソーテック社, 2016年)は、SEOとライティングの本質を学べる一冊です。Webライティングでは、検索エンジンの仕組みを理解しつつ、読者に響く文章を書くことが求められます。本書では、SEOの基本から、売れる文章の書き方まで、実践的なノウハウが網羅されています。
本記事では、本書の内容やポイントを紹介し、SEOライティングの考え方について掘り下げていきます。
SEOに強いWebライティングのポイントとは?
Webメディアには、紙媒体とは異なる特性がある。ふくだたみこ氏は、「検索される」「一瞬で嫌われる」「縦スクロール」の3つを、Webメディア特有の特徴として挙げている。なかでも「検索される」という点は、Webメディアの最大の特性と言えるだろう。検索結果で上位に表示されるためには、SEO対策が欠かせない。Web記事を執筆する際には、このSEOを意識することが、もはや必須と言っても過言ではない。
検索者の多くは、第一印象による一瞬の判断で、表示された記事を読むかを決める。ファーストビューの第一印象が良ければ、スクロールしてもらえる。スクロールして読むか、すぐに離脱してしまうかは、ファーストビューの第一印象の影響が大きい。
どんな画像を使っていて、どんなキャッチコピーなのかが、決め手になる。レイアウトや画像などの印象が良いと、検索により初めて訪れた方から閲覧してもらえる可能性が高くなるであろう。Webサイトの記事では、タイトルや見出しなどを書く際に、キャッチコピーのセンスも要求される。
紙媒体の場合は一覧性があり全体を見渡せるが、Web媒体は縦スクロールのメディア。Webサイトの場合、基本的には下へスクロールしながら読む。Webライティングでは、順番に読み進めることを前提に、ストーリーを設計する必要がある。求められる順番に情報を並べていくことが大事。スクロールしながら気持ちよく読めるような構成を心掛けることが必要だ。
Webメディアでは、記事ごとにキーワード選定をする。その際、ビッグキーワード1語を狙うより、ロングテールの複合ワードを狙うほうが、SEOライティングで失敗するリスクは減る。ロングテールキーワードとは、月間検索数が数十回のキーワードのこと。検索数が少ない代わりに、競合も少ないので、割と早く上位表示される可能性がある。
ビッグキーワードは、大手企業が上位を独占している場合があるので、ビッグキーワードによる上位表示は簡単ではない。ロングテールキーワードで記事を書くときは、ビッグキーワード以上にユーザーの意図を考えることが大切だ。ロングテールの複合ワードは、ビッグキーワードよりも検索意図が明確であると考えられる。
Webメディアにおいても、最終的には良質で有益なコンテンツを作ることが重要だ。良質とは、そのWebサイトにしか書けないオリジナルコンテンツと解釈される。検索上位のWebサイトに書いてあることが同じでは、見て回る意味がない。検索者は、Webサイトの強みやオリジナリティーを比較検討する。
有益とは役に立つかどうかということ。Googleが世界一の検索エンジンであり続けるのは、検索ユーザーが欲しがっている情報を的確に表示できるから。つまりGoogleが検索順位を決定する際に重視するのは、役に立つオリジナルコンテンツであるのかということになる。
紙媒体にしろWeb媒体にしろ、文章を書く際は、構成力や目的に応じて書き分ける文章力が必要だ。文章が長くなるにつれて、構成力が問われる。ふくだたみこ氏は、Webメディアに掲載する文章に関して、「総論・各論・結論」という文章構成を勧めている。
文章は、一般的に主観的な文章と客観的な文章に分けられる。ふくだたみこ氏は、Webサイトに掲載する文章に関しても、ページや目的に応じて、主観的な文章と客観的な文章を書き分けることが大事と述べている。
主観的な文章の代表として、日記、手紙、感想文を挙げている。ブログも主観的な文章だ。客観的な文章の代表は、新聞、レポート、取扱説明書など。コラムなどは、主観と客観を織り交ぜて書くことになる。
主観的な文章には親近感があり、客観的な文章には説得力がある。正しく理解して、書き分けることが大切だ。
書誌情報|『SEOに強い Webライティング 売れる書き方の成功法則64』
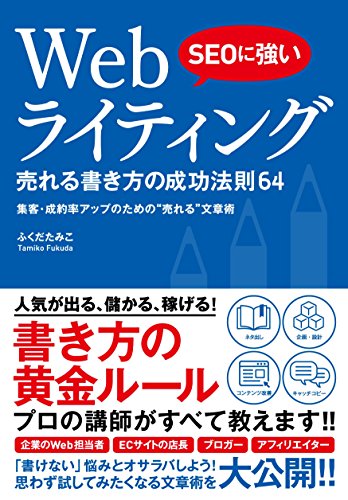
書誌事項
書名:SEOに強い Webライティング 売れる書き方の成功法則64 ―― 集客・成約率アップのための”売れる”文章術
著者:ふくだたみこ
出版社:ソーテック社
発売年月:単行本 2016年8月/電子書籍 2016年8月
ページ数:単行本 296ページ
Cコード:C3055(電子通信)


