『文学とは何か』(1950年/角川書店)は、 戦後日本を代表する知識人の一人、加藤周一氏が31歳の時に書いた評論です。この本について、さまざまな角度から考察し概要をまとめていきます。
戦後日本を代表する知識人が31歳の時に書いた評論
加藤周一氏(1919年 – 2008年)の『文学とは何か』は、1950年刊行の角川書店・角川新書、1971年刊行の角川選書を経て、2014年7月に角川ソフィア文庫から刊行されました。
「新版(1971)の序」によると、新版をつくるのに、いくらか筆を加えるとともに、1964年に文芸誌に発表した文章も最後に加えているとのこと。
つまり加藤氏が本書の大筋を書いたのは31歳の時。
氏は戦後日本を代表する知識人のひとり。
本書には、文学とは何かという抽象的な問いについて書かれています。
何が文学であるかという具体的な問いにはある程度まで答えられますが、文学とは何かという抽象的な問いに答えることはなかなか難しい。
そこで文学という言葉のなかから、もう少しあやふやでない意味を取り出そうというのが、本書の目的とのこと。
客観的な方法によって文学の本質を定めようという要求は、当然の要求。たとえば、ドイツの文芸学者は、いままでの代表的作品から、少なくとも客観的らしくみえる手続きによって、文学とは何であるかを定めようとしました。
何であったかという昔のことの話になると、客観的な議論ができます。だがそれでは人を説得するのが難しい。なぜなら、文学作品に対する評価は、時代と人によって違います。
そこで、文学は何であるかを考え、文学とは何であったかを述べるのがものの順序、というのが加藤周一氏の意見です。このように本書は展開していきます。
序盤において「文学とは作者がその体験を語るもの」という基本的な考えが示されています。ただし日常生活の体験を記した日記は、そのままでは文学とはいえません。
加藤周一氏は、文学体験を特殊な文学的なしかたで処理された体験としています。文学とは何であるかという問題は、まずここにはじまります。
文学者が特定の具体的経験に加える操作は、科学者が加える操作と正反対です。科学的体験は、日常的体験のように条件を整えさえすれば反復されます。これは、自然科学に限らず、実験の不可能な経済学などにおいてもいえることです。
対して文学者は、特殊性と具体性に注目します。そして特殊性の裏に普遍的な本質をみようとする。けっして二度と反復されない、一回限りのものとして。
文学者が語るのはあらゆる経験を具体性においてとらえた一回限りのものであり、反復されないからこそ価値があります。この文学的体験は、日常的・科学的な立場からは意味がありません。
文学は感情を描くものですが、日常生活の効用についての体験からは人間の感情の深みが現れません。
たとえば一般化することのできない特定の相手。文学的体験は文学固有のものではなく人生に固有のもの。誰の生涯にも、日常的習慣を離れて自身の心の底を覗かざるを得ない瞬間がある。世渡りの術で処理できないことを扱うのが文学。
人間と人間との関係は、すべての具体的な事件がそのものとして、かけがいのないただ一回かぎりのものとして、われわれの人格にせまり、その根底をゆりうごかし、生き方の全体を変えようとするもの
文学の価値を高めるには、ここを重視しなければならない。
文学の扱う体験は、日常生活には役に立たないものであっても、人生に役立たないということは全くありませせん。
文学とは、無限の意味について語るものであり、生涯を決定する重大な瞬間についていかに生きるべきかを深く語るもの。
しかし、言葉によって表現するものが文学者とはかぎりません。科学者も言葉によって表現し、日常生活も言葉による表現を通じて営まれます。文学者の用いる言葉は、科学や日常会話に用いられる言葉と全く同じです。
その違いは、同じ素材(言葉)に対する態度の違いによるもの。言葉に対する態度の違いは、詩と散文との間にあるものです。
言葉には意味と響きがあります。一種の符号と物理現象。二つははっきりとは区別されない。その全体を言葉として扱うことこそ、詩人の態度。
また詩句は、対象を意味する符号というより、対象から受け取ったものの実体化。これは画家が絵画を描くときと同じ。ここに詩句の本質的特徴があります。
散文は対象を意味し対象を描く。対象と一対一の対応があり、響きを含めての全体として、感覚に訴えるものではない。ここが詩句と散文とにおける表現の違い。よく散文を説明的な文章というがそのこと。
詩には実体があり、散文は実体に至らない。
詩的表現からは映像が浮かぶ。
散文は、目的を果たせば無用になり忘れてしまうことがあり、言葉と対象との正確な対応だけが問題になります。また日常的言語はややあいまいですが、科学は厳密さを必要とします。
散文で目に見えるように描こうとしても、実際の映像には及ばない。実際に見えるのが映画の魅力。散文に客観描写が可能であるにしても、映画との比較にはならず、小説的表現としてふさわしくない。
言葉には意味があります。
そして意味は想像力に訴えます。
ある風景を客観的に表現することが目的なら、記録として感覚に訴える写真という表現手段を使えばよい。逆に風景をながめる人物の感動を再現するという目的には、言葉がふさわしい。
小説は主人公の感動を描き、読者をその感動に誘いながら、周囲の風景を想像させようとするときに力を発揮します。
このように加藤周一氏は、文学の前提として、文学者が特殊な具体的な体験から出発するということを強調しました。特殊なものを、特殊性に即して追求しながら、普遍的なものに高めることが、文学に固有の方法。
態度の違いや、意味と響き、実体化、感動を再現することなどは、根本的な概念といえそうです。
加藤周一氏は、近代文学の原理について次のように論じています。
わたくしの告白でも研究でもない、わたくしにおける人間性の告白であり、研究である
言い換えれば、特殊な存在の裏に普遍的な本質をみるということ、とも。
美とは何か、人間とは何か。
文学とは、世界とわれわれとの関係を限定するもの。
文学は一方で美にかかわるとともに、真実、ことに人間的真実にかかわっています
文学が何であるかということは、美が何であり、人間が何であるかという文学以前の問題からきりはなしては考えられません。
何が美しいかということ。
何が美しいかということについては、人々によってさまざまな感じ方や考え方があります。
ここに通用するもの、自らに通用する美しさをみつける人が芸術家であるはずです
芸術家は、自らに通用する美しさを見つける。
これは容易ではない。
そのため、芸術家になることが容易ではない……
しかし、人間の精神にはたらく共通するものが見つかれば通用するはずだ。
またどんな芸術でも流行(歴史的制約)に支配されないものはないので、歴史的立場からはなれた抽象的な美学をあみだしてもものの役にたちません
日本的な美しさ。
東京都と京都の対比、日本の庭、自然の調和、等々。
季節の変化もそのひとつ。
必ずしもすぐれた人間研究家ではないが、すぐれた風景画家であり趣味人であった『枕草子』の著者
清少納言の敏感な感受性がとらえた時間とともに移りゆく自然の美しさ
ほとんど感傷的な大衆小説は、文学とはいえないかもしれません。
感傷的、つまり悲哀の感情におぼれ、センチメンタルな作品、
何が美しいかということとは、結局人間は何かということに帰着する
何が人間的であるかということ。
こちらも抽象的には論じにくい問題です。
人間的ということ、文化と文明、人間の自由。
本書は、「文学とは何であるか」という見出しの章ではじまり、「何が美しいかということ」「何が人間であるかということ」と続きます。
「何が人間であるかということ」の章の最後に、文学と直接に関係のない議論をうちきろうと思います、と綴られています。そして、直接に関係のない議論が、間接に文学とどう関係しているかということは、賢明な読者の側において容易に判断されるでしょう、と。
続いて、中盤にさしかかるあたりから、詩について、散文について、小説家の意識について語られます。
「詩について」の章では、冒頭で次のようなことが綴られています。
節の見出しが「純粋詩について」、「辞書にはどう規定しているか」という項です。
いくら理くつをこねまわしても、高遠な感情を心のなかにいだいていても、言葉を材料として詩をつくりあげることのできない人は詩人ではない
さらに、「詩と散文とのちがい」についての、次のような文章も印象的です。
詩人は、まず世界を直接に、すなわち言葉を媒介とせずに感じ、その感じと等価値的な言葉を探します
反して、散文家は、はじめから世界を、言葉を通してながめます
また、「純粋詩」についての項では、次のようなことが書かれていました。
いちばん純粋な詩がどういうものかを考えると、叙事詩でもなく、まして劇詩でもなく、叙情詩です。
なかでも、フランスの象徴派の詩。
「日本の純粋詩」についての節では、次のようなことが書かれていました。
詩人が無常であると観ずる心は、自然のなかにはなく、人生のなかにあります。
誰にとっても同じ自然ですが、人生はその人のもの。
「散文について」の冒頭は、次のような文章です。
節の見出しが「西洋文学の文体」、項の見出しが「散文とは何か」です。
散文とは、描くもの、描くことによってその人と世界との関係を定義するもの、あるいはその人にとっての世界を意味づけけるもの
続く「個体と文体」という見出しの項には次のようなことが書かれていました。
文体は、散文の形式であって、作家の感受性と思考の方法とをもっとも深く、もっとも直接に反映します
同時に、作家の住む時代と社会とに固有でもあるはず、とも。
「散文について」の章の後半は、日本。節の見出しは、「日本の散文」です。「明治以前の文体」からはじまり、「日本語の構造」「西洋の影響」「近代作家の文体」について。
「小説家の意識について」の章は、「日本文学の限界について」という節からはじまります。はじめに「近代社会と文学」という項です。
冒頭は阿部知二氏から聞いた話として、阿部氏の説の要約が書かれています。これは、日本において、ヨーロッパのような近代的な小説をつくることができるかという話です。
近代についていえば、ヨーロッパの小説は市民社会の表現でした。対して明治以降の日本文学は、封建的文化をくずしながら、一方では市民社会を完成せず、典型的な市民を生むにいたりませんでした。これは、小説の問題ではなく、歴史の問題です。
次の節「広場の意識と孤独の意識」の最後は、次のような文章で締め括られます。
小説はその世界に住んで、その世界を描こうとしている
さらに、次の節「文学における社会的意識」においては、要約すると冒頭で次のようなことが書かれています。項の見出しは「社会的意識」です。
小説は、ある特定の個人を描くもの。階級にせよ、人類にせよ、あらゆる社会は、個人の精神に反映するかぎりにおいてのみ、小説家の対象となります。
歴史的叙述、また心理学や社会学の方法は、小説家の利用できるものですが、小説家たらしめるものではありません。小説家は、固有の対象として具体的な個人をもち、具体的な個人を表現するために固有の方法を用います。
「文学における社会的意識」という節の、3つ目の項は「小説の技術」です。とくに印象に残る箇所は、次の通りです。
充分な資料というものは存在せず、資料や条件を列挙すれば、常に不足の印象をあたえるほかはありません
全体をその多様さと多面性とのままに考えたり描いたりすることは不可能で、その本質を直感するほかに全体としての社会を捉える方法なないでしょう
そして、「自己の内部へ深く降りてゆくことによって一般に人間的なものを探りあてれば、小説にいかなる社会を背景として用いようと普遍的な文学をつくることができるはずです」という文章が、「小説家の意識について」の章の最後の段落に記されています。
1950年刊行時の最終章の見出しは「文学とは何であったか」です。
つまり、文学史。
このなかで加藤周一氏は、「詩、小説、劇、文芸評論だけを文学と考え、文学史の対象をその範囲に限定するのは、おかしい」と述べられています。
日本の明治文学史は、小説家の集団を分類することなどは省略しても政論家中江兆民、宗教家内村鑑三、美術史家岡倉天心にページを割いて割きすぎることはなかろうといいたい
ヨーロッパの文学史が、扱う対象の範囲を、そのまま日本の文学史にあてはめることでさえも、日本の事情にふさわしくない
せまい意味での文学(詩・小説・劇等)が、明治大正の日本文化のなかで演じた役割は、ヨーロッパの近代文学が、ヨーロッパの文化のなかで演じた役割よりも、比較にならぬほど小さいものです
せまい意味での文学が、独立の文化形態としていちおう自律的な発展を示しはじめたのは、ヨーロッパでもロマン主義以後のこと
加藤周一氏の『文学とは何か』は、1971年刊行の新版において、加筆されるとともに、1964年に文芸誌に発表した文章も最後に加えています。見出しは「文学の概念についての仮説」です。「新版(1971)の序」によると、旧版の内容と相補う点があるだろうと考えたからとのこと。
内容は、言語と文学の論争について。副題に示していますが、この議論に対する加藤周一氏の論が綴られています。
文学は、言語という象徴の体系による表現
他の言語による表現と区別するためには、第一に、表現されるものの違いによるか、第二に、通じ合いの相手の違いによるか、第三に、表現の違いによるか。
第一の要点は、表現されるものの違い、文学の表現する経験。
文学は具体的な経験の具体性を強調する
分類の不可能な、一回かぎりの具体的な経験が、文学の典型的な対象
これは科学の対象とはならない。科学が成りたたぬところにおいて、文学が成りたつのではっきりと区別できる。しかし、日常生活から区別することは困難。日常生活の経験は、文学的な面をふくむと同時に、また科学的な面もふくむ。
文学的経験は、単に具体的な、一回かぎりの経験なのではなく、それを通して当事者の人生の全体、つまりその人の世界の全体に対する態度が現れざるをえないような経験
科学も、文学も、世界の全体にかかるもの。
日常生活は、世界の部分にかかるもの。
大衆小説について、文学と考えるか。
この議論についても、これ等の考察に関連する。
歴史的記述や哲学的著作が文学になるのは、それが人間の世界の全体に対する態度をふくむから
第二の要点は、通じ合い、文学が訴える相手。
この検討は、文学史的展開を跡づけるために有益。
第三の要点は、文学的な表現における言葉の機能。
この検討は、詩的なるものと散文なるものとを区別するために有益。
ことばの機能を極度に利用することによって、「いわく言いがたきもの」を表現しようとする努力は、小説家よりも詩人において極まる
一部抜粋すると、文学的な散文と、非文学的な散文とを区別することはできない。文学的散文はすべて詩的な要素をふくんでいるということはできるだろう。
加藤周一氏によると、第二、第三の点については、文学的表現を、そのほかのことばによる表現から区別するためには、役立たない、とのこと。
文学的表現を特徴づけるためには、第一の点にかえらなければならない、と。抽象的普遍性においてではなく、具体的特殊性において、表現しようとすること。その表現が作者の世界の全体に対する態度を前提として。この二つの特徴の両方のそなわったことばによる表現が文学である、と。
なお、本書に解説があり、これは池澤夏樹氏によるもの。解説の書き出しは、「ずいぶん正面切ったタイトルの本だ、とまず思う。」
本書の章立ては、章・節・項ですが、第一章の見出しが「文学とは何であるか」で、第一節が「客観的な方法」、第一項が「文学と非文学」。
池澤夏樹氏は「客観的な方法」から入っていることについて、次のようなことを述べられています。
果たして文学は客観的な方法で定義できるのだろうか?
もともと客観性とは科学の方法論である。
解説文にも記されているが、加藤周一氏は医者だったから科学の方法論を思考の道具として身に付けていたことは、知っておくべきことでしょう。
言うまでもなく文学はまずもって主観の装置。
「普遍的な文学の定義を求めて客観に走ったが、そこから主観の方へ少しずつ戻る形で議論は進む」、と解説されています。
実際にこの記事で述べてきた通りです。
池澤夏樹氏の解説文のなかでは、次のような言葉も印象に残りました。
客観と主観の隙間に文学はある。
文学を論じる時にすべての基礎として必要なのは読む力。
書誌情報|『文学とは何か』
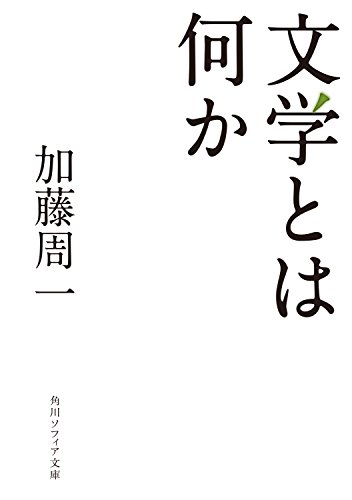
書誌事項
書名:文学とは何か
著者:加藤周一
発行:KADOKAWA
発売日:角川書店・角川新書(旧版) 1950年、角川選書(新版) 1971年9月、角川ソフィア文庫 2014年7月
Cコード:C0390(文学総記/角川選書)、C0195(日本文学・評論・随筆・その他/角川ソフィア文庫)
ページ数:角川ソフィア文庫 208ページ
紙書籍
電子書籍


