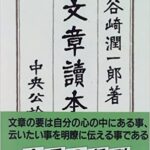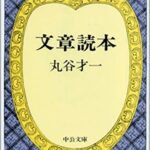川端康成氏の『新文章読本』について、その魅力を掘り下げていきます。
生きた文章を考える
川端康成氏(1899-1972)の考える文章道とはどのようなものだったのか。川端氏の『新文章読本』の大部分は、昭和24年(1949)から昭和25年(1950)にかけて、雑誌『文藝往来』に連載されたものである。本書は、1950年にあかね書房より単行本として刊行された。
文章は単なる技術ではない。文章は即ち人。一技術とみなすと文学を乏しくしてしまう。そして文章は、人と共に変わり、時と共に移る。文体の古び方は早い。
しかし、底に流れるものは案外不変なものである。古い文章を正しく理解し、新しい文章を知ることは、生きた文章を考える上での宿命と言えよう。
小説は、言葉を媒体とする芸術である。文章と文体が、小説の重要な構成の要素であることは間違いない。文芸は、作者の心理活動が、表現に達することで完了する。
芸術活動は、創作と受用の二つの連結点に起きる。創作家は表現し、鑑賞家はその表現に接するのだから、文学においても表現は重要な意味を持つ。
我々は、表現を通じて作者の現わそうとした内容を知ることができる。作者が、自分の作品について、いつ、いかなる芸術的意図をもって着手し、何を表現したかを、詳しく説明したところで、それは多少の便宜。
作者にとっても、読者にとっても、千万の説明よりも、その作品の表現のほうが重要なのである。表現こそが作家と読者との心理を結ぶ唯一の一点である。ただし芸術研究家の立場からするといささか異なるであろう。
絵画が線や色によって表現し、音楽が音によって表現するように、小説は文章によって表現される。いかに巧みなプロットでも、表現方法が拙劣ではその意図の半分も伝わらない。芸術は表現が大切なのである。小説は言葉の精髄を発揮することによって、芸術として成立する。ゆえに作家は、言葉との格闘で生涯を終える。
おそらくは、内容や思想の方が重要と考える方もいるであろう。しかし、本書はあくまで文章読本として、芸術的な面を重視している。
文章・表現を一種の技巧のように考えるのか、作家修行を文章修行と考えるのか、二つの考え方のどちらが正しいとは軽々しく言えない。ただし、言葉・文章・表現を粗雑に考えることは避けるべきであろう。
文学上の各流派には、その流派ごとの文章がある。これは、一人ひとりの作家が、自分の文章を持ち、文体を持つということである。独自の文章・文体を持たない限り、傑出した作家にはなり得ない。傑出した作家は、より多く独自の優れた文章、優れた文体を持っている。また、新しい思想・内容は、それにふさわしい、新しい表現、新しい文章を必要とする。
文章・文体は絶対ではない。更に研究し、更に進歩しなければならない。
優れた作家は、自分の文体と文章を持つ。その源は、語彙に見られる。文体は一つには使用する単語の差異から生まれるものだ。作家の個性は、単語ひとつからも究明できる。作家は大方、語彙力があるが、使用する言葉に好みはあるはずだ。
作家にとって、文章は永遠の謎であり、永遠の宿題であろう。
我々は、つねに新しい外来思想を取り入れてきた。そのため、新しい文章を生まなければならない。反面、つねに異国の言葉と口語との間にある、永久に結びがたい一点をも考えなければならない。英語について述べれば、イギリスとアメリカですら文章に違いがある。言語の文法や文化が大きく異なる日本語との隔たりは大きい。
日本語は語彙に乏しい。それを補ってくれたのは外国語であるが、限界に達すればむしろ混乱をまねくこともある。また日本語の語彙の乏しさは、国民性を反映しているとも考えられる。
日本語は、簡素に余情に向かって発展してきた。日本語の従来の長所は、説明よりも、むしろ象徴であった。国民性は、精神的なことのみではなく、気候、風土、体格、習慣等にも裏打ちされている。
単語のよき選択はよき文章の第一歩。用語も文体もすべて個性である。優れた文章・文体は、最も己に適しているものである。
文章の特徴にセンテンスの長短がある。これは、用語と同様、作家の作風であり、文学観につながる。短いセンテンスの文章は、典型的な散文となるか、多分に詩的な情趣を含む。短いセンテンスの作家は、会話が巧妙であることも多い。長いセンテンスの作家は、詳悉法の傾向を帯び、修辞を愛し、複合文を駆使する。
センテンスの長短に関しては、優劣を決すべきではないが、短所についても知っておくべきだ。短いセンテンスは、時として色も匂いもない、無味乾燥で、詩情も空想もなく、単調な文章となる危険を持つ。長いセンテンスは、修辞がない常識だけの文章になった場合、おそらくは冗長なだけで、退屈なものになるであろう。
省略法的な短いセンテンスは短篇小説に適する。詳悉法的な長いセンテンスは長篇の傾向を帯びる。
文章は、己の心緒に最もふさわしく、一番己の好きな文章であることが大切だ。ただし優れた文章は、あらゆる用語を駆使し、あらゆるセンテンスを自在に使いこなし、種々の風趣を含ませているであろう。
優れた文章を読み、それぞれの長所を見つけることから、第一歩が見出される。凡百の理論よりも、まずは個々の作家の文章から確かめた方がよい。文章は、技巧よりも情熱、姿よりも心。優れた作家が独自の文章と文体を持つことは、その作家の生涯とも似ているようだ。処女作を頂点に、あとはそのバリエーションである場合も多い。
書誌情報|川端康成『新文章讀本』
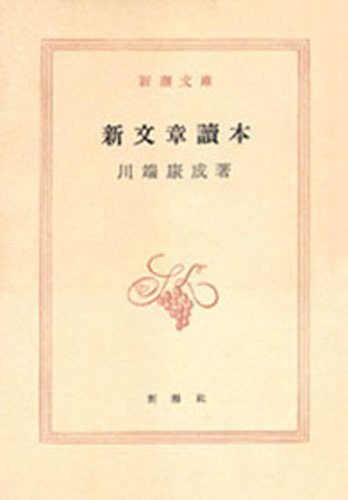
書誌事項
書名:新文章讀本
著者:川端康成
出版社:あかね書房/新潮文庫/タチバナ文芸文庫ほか
発売年月:単行本(あかね書房)1950年11月/新潮文庫 1954年9月/タチバナ教養文庫(タチバナ文芸文庫)2007年12月/電子書籍(新潮文庫)2012年12月
ページ数:新潮文庫 112ページ/タチバナ文芸文庫 216ページ(4編を収載)
Cコード:C0390(文学総記/タチバナ文芸文庫)
タチバナ文芸文庫の内容:「新文章読本」(昭和25年10月)・「文章学講話」(大正14年7月)・「新文章論」(大正12年11月)・「新文章論」(昭和27年4月)
紙書籍
電子書籍