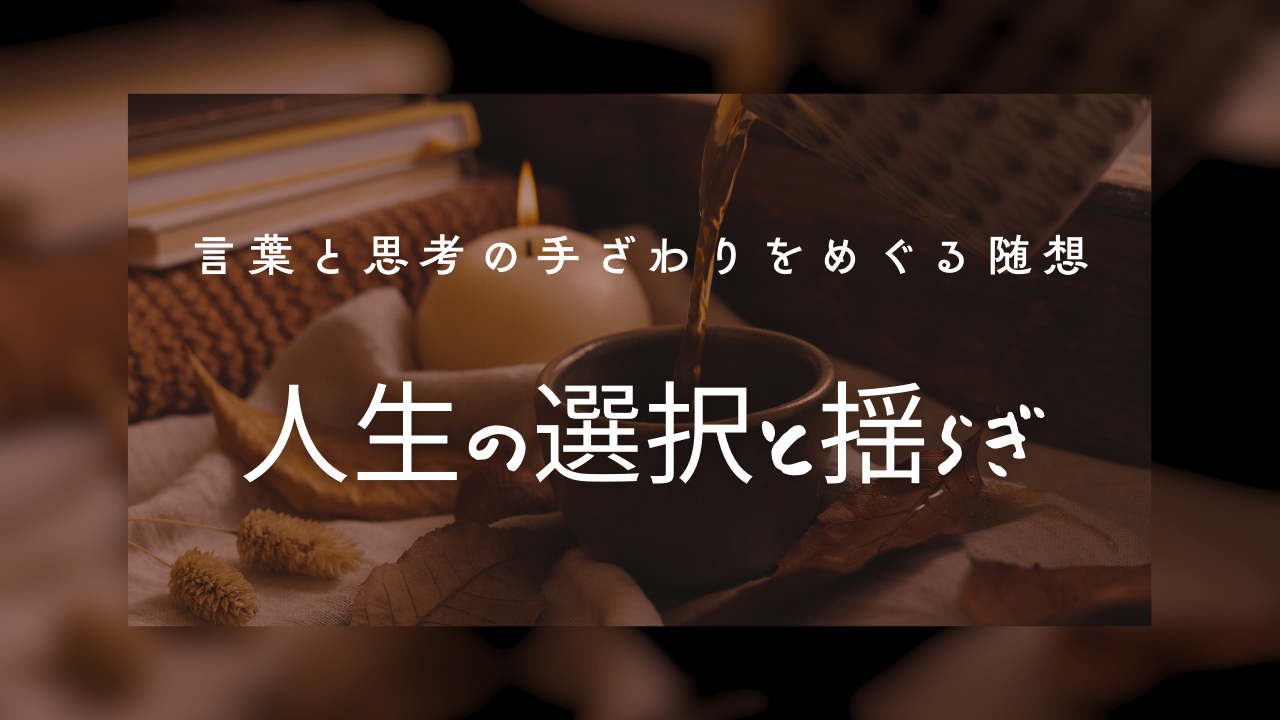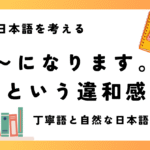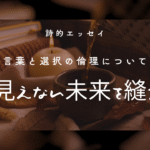選ぶことについて考えるとき、私はいつも、小さな境界の手前で足を止める自分に気づく。
境界線に立ち止まる ― 選ぶこと、考えること、そして日々
日常のなかには、ふと足が止まってしまう瞬間がある。
何かを選ぶ前に、見えない境界線の手前で呼吸を整えるような、そんな感覚だ。
まだ起きていないはずの出来事が、どこかで見た夢の影のように胸に忍び寄ることさえある。
言葉はときに道標のようで、ときに迷路のようだ。
整然と並んだ理屈や思考の背後には、
「もし明日、違う道を歩いたら」という、静かな気配がひっそり潜んでいる。
私たちはきっと、理念と現実のあいだの縫い目をたどりながら生きている。
その縫い目には、迷いや逡巡、手探りの跡がひそやかに刻まれている。
間に立つということ
人生でも、人はしばしば選択の“あいだ”に立つ。
ある道を守ろうとする自分。
新しい道を探しに行く自分。
そして、その両方を見つめながら静かに席を整える自分。
“間に立つ”とは、中心を占めることではない。
沈黙しながら風の向きを読み、揺れを抱えたまま歩く姿だ。
安定や妥協ではなく、感覚を研ぎ澄まし続ける態度に近い。
言葉と思想の手触り
「こうあるべき」という言葉は力を持つ。
けれど、便利な言葉ほど、人の思考を短絡させることもある。
人はひとつの思想に完全に寄りかかることはできない。
矛盾も迷いも、同じ胸の内にそっと同居している。
大切なのは、言葉を捨てることではない。
その言葉がどんな空気の中で生まれ、どんな時間をくぐり抜けてきたのか――
その手触りや匂いに、いったん指先を触れさせてみることなのだと思う。
沈黙の質感と選択の影
文学や歴史をひもとくと、
人は時に声を上げられず、沈黙を選んでしまう。
生きるために選んだ道と、選ばなかった道。
その二つが胸の奥で折り重なり、静かな影を落とす。
結果の裏側には、数えきれない「未遂の選択」と「言えなかった言葉」が横たわっている。
沈黙を責めるだけでは見落としてしまうものが、確かにある。
学ぶこと、抱きしめること
過去を学ぶことは、誰かに責任を押しつけるためではなく、
その時代に生きた人々の息づかいを抱きしめるためだ。
何が起きて、世界がどちらへ傾いていたのかを知る。
そのうえで今日をどう生きるか、どの倫理を選び取るかを考える。
忘れないために学び、
学びながら、また選び直す。
それでいいのだと思う。
小さな旅、手触りのある世界
ふと身の回りに目を向けると、
遠い土地の時間や湿度が、日々の暮らしにそっと混ざり込んでいることに気づく。
糸のより方、縫い目の柔らかさ、材質の手触り――
見えない記憶や季節の匂いが、その奥に潜んでいる。
“どこで何が作られたのか”を意識することは、
遠い世界を一瞬だけ自分の生活へ引き寄せる小さな旅なのかもしれない。
終わりに ― 迷いながら生きる
人生も世界も、あまりに大きく、手の届かないものばかりだ。
それでも、人は小さな選択を積み重ねながら歩いていく。
どの情報を受け取り、
どんな言葉を使い、
どんなものを手に取るのか。
迷いながら選び、
選びながら学び直す。
その揺らぎの中にこそ、
私たちが生きていくための“手触り”があるのだと思う。