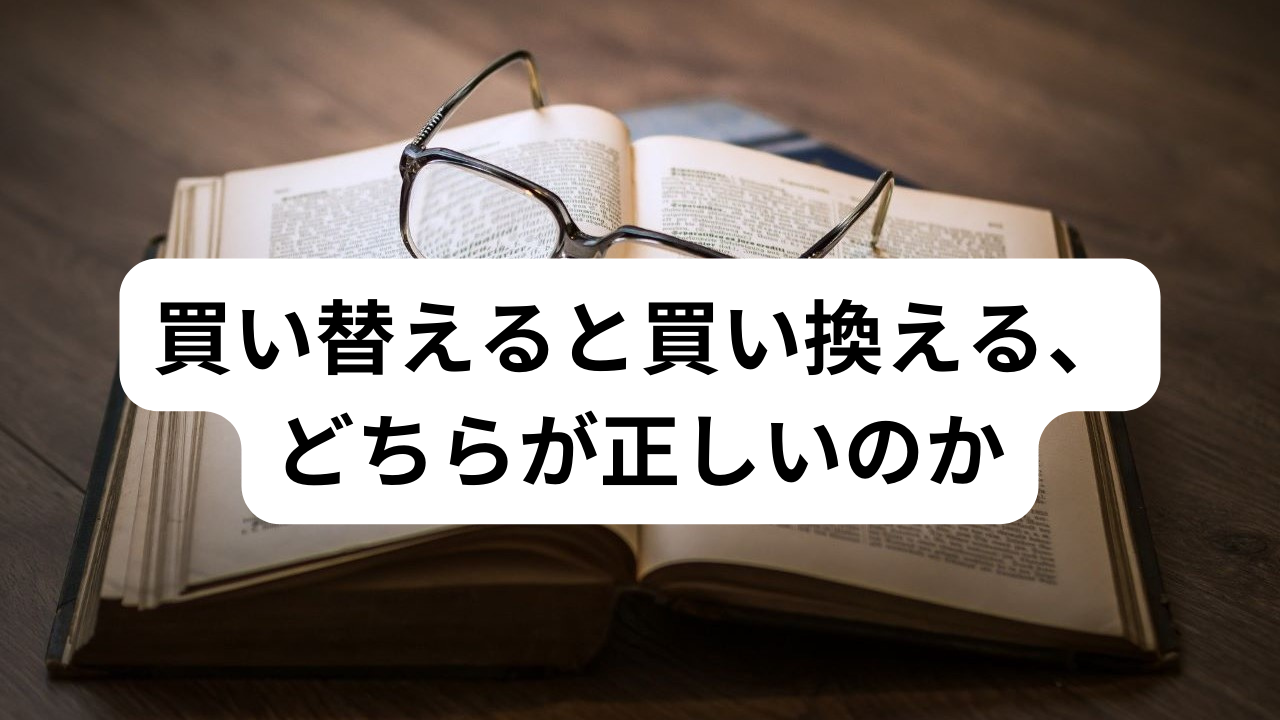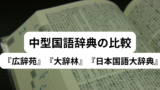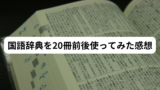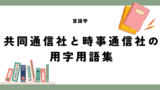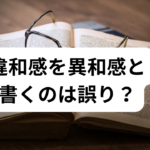この記事では、複合語の「買い替え」と「買い換え」について、どちらの表記を使うべきか、さまざまな角度から掘り下げていきます。
多義語<和語の動詞>の「か・える」(変える・代える・替える・換える)
複合語の「買い替える」と「買い換える」、どちらの漢字を使うべきか
「買い替える」と「買い換える」、どちらの漢字を使うべきでしょうか。近年は「買い替える」の表記が増えてきました。「買い換える」と書いていた方は、「買い替える」という表記を目にすることが多くなり、どのように感じ、どのように対応されていますか?
所有している辞典類で調べたところ、「買い換える」と「買い替える」の両方が載っている場合と、「買い替える」のみを載せている書籍に分かれます。「買いかえ」には触れずに、「かえる」のみに触れている場合もあります。
どちらでもよいとする国語辞典がある一方、辞典や用字用語集によっては「買い替える」のみ用例に載せています。よって、どちらかというと「買い替える」のほうがよいと思うかもしれませんが、そうとは言い切れません。なぜなら中型国辞典を含め、多くの国語辞典で「買い換える」も載せているだけでなく、「買い換える」を「買い替える」よりも先に記載しているからです。
さらに、文化審議会国語分科会の資料のなかでは、「買換え」が使用されていました。例えば、『新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)』(令和3年3月12日)という資料です。また、国税庁のウェブサイトや経済産業省の家電リサイクルに関する資料などでも「買い換え」が使用されています。
それに「代える」と「換える」を入れ替えることはできませんが、「替える」については両方の言い回しに使うことができます。また、古くなったり故障したりして交換するという理由から、「買い換える」のほうが「買い替える」よりもしっくりくる方も多いのではないでしょうか。一方、新しいものに入れ替わるという感覚が強いと、「買い替える」が使われるのかもしれません。
報道界では、大抵「買い替える」が使われているはずです。報道の影響は強く、「買い替える」を使う方が増えているのでしょう。さらに、一般人向けの国語辞典においても、売り上げの上位を占める『三省堂国語辞典』『新明解国語辞典』『岩波国語辞典』が、「買い替える」のみを載せています。
新聞の広告・チラシや大型小売店のポスター、テレビ番組のテロップなどでは「買い替える」の表記をよく目にします。その一方で、官公庁の文書や小説など、どちらかというと硬い文章では「買(い)換える」という表記が多いようです。小説に関しては、作家あるいは作品によって「買い換える」と「買い替える」に分かれます。
一部の国語辞典や用字用語集では、「買い替える」のみ用例に載せていますが、最近刊行された本や雑誌でも、両方の字が使われています。
中型国語辞典をはじめ、多くの国語辞典では「買い換える」を優先
『大辞林 第二版』(松村明, 三省堂)、『大辞林 第三版』、『広辞苑 第七版』(新村出, 岩波書店)、『精選版 日本国語大辞典』(小学館国語辞典編集部)の、4冊の中型国語辞典において、「かい-か・える」には「買い換える」と「買い替える」の両方が載っています。
しかも、記載の順番は、「買い換える」が先で「買い替える」が後です。これは、多くの場合、「買い換える」の方がより的確と取れそうです。「買い換える」という複合動詞の意味は、新しく買って、今までのものととりかえる、ということ。買うという行為を重視するなら、「買い換える」が適切といえそうです。
『大辞林』(三省堂)
『大辞林 第二版』と『大辞林 第三版』(アプリ版 スーパー大辞林3.0)では、「替える」と「換える」の表記について、次のように説明しています。
「替える」については、「同種・同等の別のものと交替させる」とし、「商売・水槽の水・シーツ・メンバー」を用例に使っています。「換える」の説明は「ある物を与えて別のものを得る」とし、「宝石を金に換える」という用例を載せています。
さらに『大辞林 第三版』では、「かえる(替・換・代・変)」の表記についての追記があります。「替える」が「同種の物といれかえる」の意で、「換える」が「他の物ととりかえる、交換する」の意であると説明しています。「代える」は、代用する、代理とする、という意。「変える」は、状態を変化させる、場所を移すという意です。
そして、大辞林の「かい か・える」の項目には「買い換える」と「買い替える」の両方が記載されています。他の国語辞典でも同様ですが、記載されている順番は「買い換える」が先で「買い替える」が後です。
これは、名詞の場合も同様であり、【買い換え・買い替え】という記載です。
「換」と「替」の両方の漢字が使われる複合動詞は多数存在します。
その中で「換」を先にしているのは、「言い換える」「置き換える」「乗り換える」「引き換える」。
逆に「替」を先にしているのは、「入れ替える」「書き替える」「切り替える」「組み替える」「差し替える」「取り替える」でした。
また、「替」のみを使用している複合動詞として、「掛け替える」「着替える」「着せ替える」「繰り替える」「仕替える」「挿げ替える」「住み替える」「掏り替える」「立て替える」「建て替える」「作り替える」「付け替える」「積み替える」「詰め替える」「塗り替える」「履き替える」「張り替える」「葺き替える」「振り替える」「巻き替える」「召し替える」「持ち替える」「遣り替える」「読み替える」が挙げられます。
「変」と「替」を使用する複合動詞もあり、それは「吹き変える」と「見変える」です。ただし、名詞の場合は「吹き替え」のみです。
これ等の事実は、「買い替え」という表記が増えていることと関連があるかもしれません。
なお、”みかえる”については、【見変える・見替える】のほかに、【見返る】がありますが、もちろん別項目です。
『広辞苑』(岩波書店)
対して『広辞苑 第七版』には、「替」はある物にかえて別のものにする、「換」は物をとりかえる意で使うことが多いと書かれています。
『広辞苑 第七版』の「か・える」の項目には、【替える・換える・代える・変える】があり、❶は《替》《換》《代》、❷は《変》です。❶《替》《換》《代》については、次のような補足がありました。
「替」は、ある物にかえて別の物にする、「換」は、物をとりかえる、「代」は、他の物にその役目をさせる意で使うことが多い。
そして、「かい-か・える」の項目には、「買い換える」と「買い替える」の両方が記載されています。
『精選版 日本国語大辞典』(小学館)
『精選版 日本国語大辞典』には、「か・える(代・換・替・変・易)」の項目があり、大きく❶「代・換・替・易」と❷「変」のグループに分けています。そして、❶「代・換・替・易」については、次の通りに解説しています。
① ある物を与え、その代わりに他の物をもらう。交換する。ひきかえる。とりかえる。
② 前からあるものや、決まっているものをやめて、新しく別の物にする。とりかえる。交代させる。また、あるものの役目を他のものにさせる。代理をさせる。
③(「…にかふ」の形で)ある事のために、…を犠牲にする。…と引きかえにする。
④飯、菜など器にある分を食べて、また新しく盛り入れる。おかわりをする。
⑤古い水を外へ汲み出す。また、汲み出して新しい水を入れる。
「かい-か・える(買換・買替)」の項目には、新しく買って、今までのものとかえる、という解説がありました。ただし、引用は嘉暦3年(1328)の文書であり、「かいかえ」の箇所は平仮名でした。
※『日本国語大辞典 第二版』の編集委員は、北原保雄・久保田淳・谷脇理史・徳川宗賢・林大・前田富祺・松井栄一・渡辺実 各氏
※『精選版 日本国語大辞典』は『日本国語大辞典 第二版(全13巻+別巻)』の成果を全3巻に凝縮したもの
※『日本国語大辞典』初版の編集顧問は、金田一京助・新村出・諸橋轍次・佐伯梅友・時枝誠記・西尾実・久松潜一・山岸徳平 各氏、編集委員として200名以上の執筆者が加わった
「買い換える」と「買い替える」の両方を載せている国語辞典が多い
多くの小型国語辞典でも「買い換える」と「買い替える」の両方を載せています。『新選国語辞典 第十版』(金田一京助・佐伯梅友・大石初太郎・野村雅昭・木村義之, 小学館, 2022年2月21日発行)、『明鏡国語辞典 第二版』(北原保雄, 大修館書店, 2010年12月1日発行)、『新潮現代国語辞典 第二版』(山田俊雄・築島裕・白藤禮幸・奥田勲, 新潮社, 2000年2月5日発行)は、「かいか・える」という見出しの後の表記欄は【買い換える・買い替える】となっています。記載の順番は、中型国語辞典4冊と同様に「買い換える」が先で「買い替える」が後です。
厳密には「買い換える」であるが「買い替える」という表記も使われているという解釈ができそうですが、そうとは言い切れません。理由は、次の章で説明する通りです。
テレビや新聞などで「買い替える」の表記が増えている理由
新聞の広告・チラシや大型小売店のポスター、テレビ番組のテロップなどでは「買い替える」の表記をよく目にします。この傾向が表れている小型国語辞典も多く、通信社の用字用語集においても同様の事がいえます。
共同通信社『記者ハンドブック 第13版』と時事通信社『最新用字用語ブック 第7版』
まずは『記者ハンドブック 第13版』(共同通信社)と『最新用字用語ブック 第7版』(時事通信社)の「かえる・かわる」の項目についてです。
『記者ハンドブック』には、換が「AとBを交換する」場合で、替が「新しく別のもの・行為にする」場合であることが記されています。同様に『最新用字用語ブック』では、換が「あるものを渡して別のものを受け取る、換金、交換、置換、転換など」で、替が「前の物事をやめて別の物事をする、新しいものにする」場合であることが記されています。これに従えば、「買い替える」となります。どちらの用字用語集にも、用例として「買い替え」を載せています。
『記者ハンドブック』と『最新用字用語ブック』では、「取り換え」と「入れ替え」のような書き分けもしています。新しいものというニュアンスがあるので「買い替え」と「入れ替え」になるのに対して、交換のニュアンスがあるので「取り換え」ということでしょうか。
対して、『広辞苑 第七版』では「取り替える」です。そして用例に「部品を取り替える」という文があります。しかも、「取り換える」という表記は載せずに、「取り替える」のみです。『大辞林』『精選版 日本国語大辞典』では、両方の表記を載せていますが、順番は「取り替える」が先です。
それに、滅多に使われない表現かもしれませんが、大江健三郎さんの作品のなかに『取り替え子(チェンジリング)』というタイトルの長編小説があります。人に対しては「替」の字が使われます。
『記者ハンドブック』では、「入れ替え」について統一用語の記号がありました。統一用語とは、「二つ以上の表記があるもので、その一方を統一的に使うもの」(共同通信社『記者ハンドブック 第13版』より)、あるいは「二つ以上ある表記のうち、報道界が統一使用する語」(時事通信社『最新用字用語ブック 第7版』より)のことです。
『記者ハンドブック』の「替」の項目には、「入れ替え」のほかに「着替え」と「切り替え」にも統一記号がありました。「代」「変」「換」の項目には、統一記号はありません。更に何カ所かページをめくると、例えば「充分」に対して「十分」を使うという指示がありました。
ただし、『最新用字用語ブック』については、「代」「変」「換」「替」のいずれにも統一記号はありません。「充分」に対する「十分」などについては、統一記号があります。
また、換気のために空気をいれかえるときは、「空気を換える」と書きます。つまり、「空気をいれかえる」という表現を使わずに、「空気を換える」と書いたほうがよいのでしょう。もしくは、“換気”です。
『記者ハンドブック』と『最新用字用語ブック』に関しては、新聞表記のルール作りが本来の目的です。多くの記者が執筆する原稿の表記を統一させることが目的のため、どちらか一方を推奨した結果とも言えそうです。
家電製品や自動車、携帯電話などは、古くなったり故障したりすると、同種・同等のものに取り替えます。近年は、まだ使えるものを処分して新しい製品を購入することもあります。こういったニュアンスを反映した結果として、「買い替え」が使われることが多いのではないでしょうか。入れ替えと同様のニュアンスで「買い替え」が使われるのかもしれません。
『三省堂国語辞典』
『三省堂国語辞典 第七版』(見坊豪紀・市川孝・飛田良文・山崎誠・飯間浩明・塩田雄大, 2014年1月10日発行)には、次のような説明があります。
「替える」に関しては、①②③④に分け、②の説明が「次の、新しいものにする」です。そして用例のひとつが「買い替える」です。たしかに、次の新しいものならば「買い替える」となるでしょう。ただし注意点として、三省堂国語辞典は用例主義的な解釈と項目が多いようです。
また、名詞「かいかえ」の項目もあります。
かいかえ[買い替え]
新しく買って、前のものととりかえること。「―需要(ジュヨウ)」
用例を採取することを重視しており、対象は「新聞・雑誌・書籍・放送・インターネット・会話・街の看板など(『三省堂国語辞典 第七版』の序文より)」です。
この事を確認するために、漢和辞典『漢字源 改訂第五版』(学研)を引いてみました。すると、「替」の意味については「かわる、次のものと入れかわる」と記載されています。「次の、新しいもの」と「次のもの」という、ニュアンスの違いがあります。一方、『漢字源 改訂第五版』で「換」を調べたところ、「かえる、かわる、中身をすっかり入れかえる、取りかえる、入れかわる」と記載されていました。
『三省堂国語辞典 第七版』において、「換える」に関しては、①②③に分けています。①は「相手にものをわたし、別のものを受け取る、交換する」、②は「今までのものをやめて、ちがったものを選ぶ」、③は「今までとは、ちがった場所・部署に置く」です。
用例としては、①が「本をおかねに換える」、②が「ことばを換えて言えば・置き換え・乗り換え」、③が「配置を換える」です。
なお、『三省堂国語辞典 第七版』では、「買い替え」と「入れ替え」は「替」のみ記載していましたが、「とりか・える」に関しては、「取り換える」と「取り替える」の両方を記載しています。
『三省堂国語辞典 第七版』は、「代える」「変える」「換える」「替える」を別々の見出しにして、さらに「返る」「帰る・還る」「孵る」等も、丁寧に解説しています。項目を分けているという点では、使い分けを明確に提示しているといえるでしょう。ただし、好みの問題もあるでしょう。
『岩波国語辞典』
『岩波国語辞典 第七版新版』では、「買い替える」という動詞の記載があります。
『岩波国語辞典 第七版新版』(西尾実・岩淵悦太郎・水谷静夫, 2011年11月18日発行)の「はじめに」においては、この事に関係しそうなことが、基本方針として記されています。辞書の第四の特色として、「漢字による表記は、実際の文章においてそのように書く習慣のあったものに限った」という記述です。しかし、実際は「買い換える」という表記が広く使用されています。
よって、どちらかというと、第一の特色である「現代生活に必要なもの」という記述が関係しそうです。生活の場面では「買い替える」という表記が多用されています。ただし、これについても、国税庁のウェブサイトや経済産業省の家電リサイクルに関する資料などで「買い換え」が使用されているという事実があります。もっとも、文化審議会国語分科会の資料のなかでは、「買換え」が使用されていました。なお、第二の特色は漢字の働きを明確にすること、第三の特色は一語一語の基本的な意味を解明することです。
実際に『岩波国語辞典 第七版新版』で「かいかえ-る」を引くと次のように記載されています。釈義部分が「新しいものを買って、古いものを取り替える」。用例が「テレビを—」です。よって“取り替える”というニュアンスが強いことと、“取り換える”と書かずに“取り替える”と書く結果ともいえそうです。
また、「か-える」については、①【変える】と②【代える・換える・替える】に分け、②については更に㋐㋑㋒に分けています。
㋐それを取り除き、そこに新しいものを使う。【換・替】「部品を—」「背に腹は—・えられない」
㋑(及ばずながら、本格な)ものの役目をさせる。代理させる。【代】「蕪辞を連ねて祝辞に—・えます」
㋒甲の所のA、乙の所のBを、甲の所にB、乙の所のAがあるようにする。とりかえる。交換する。【換・替】「おむすびとかきの種を—」「円をドルに—」
そして、原義は㋒、と記されています。
『岩波国語辞典 第七版新版』において、「買い替える」と記載されているのは、近年の生活環境から用例を採取した結果といえそうです。
『新明解国語辞典』
『新明解国語辞典 第七版』(山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・山田明雄・上野善道・井島正博・笹原宏之, 三省堂, 2012年1月10日発行)も、「買い替え」「買い替える」と記載している辞典です。
かい かえ【買い替え】
車や家電製品などの耐久消費財を新しく買って、それまでのものと取り替えること。「テレビもそろそろ—の時期だ」
『新明解国語辞典』は、語釈の段階ですでに具体的なのが特徴です。
事実として、自動車販売店や家電量販店では、「買い替え」という表記が使われています。
「か・える」については、「他動詞下一段活用」と「自動詞五段活用」に分けています。
か・える(他下一)
❶【代える】
①何かを得た代わりに、それと等価なほかの何かを与える。「物を金に—」
②古いものを使うのをやめて、新しいものにする「手を代え品を代え」
③ほかのもの役割(位置・場所)に自分がなったり行ったりし、逆に相手が自分のもとのの役割(位置・場所)になったり行ったりする。「命には代えられない/背に腹は代えられぬ/攻守所—」
表記 「替える・換える」とも書く。
➋【変える】状態・位置を前と違ったものにする。「形(目先・見方・方針・顔色・目の色・血相)を—」
❸〔「動詞連用形+—」の形で、接尾語的に〕今までしていたのをやめて、新たに何かをする。「書き—・作り—」
表記 ❸は、「替える・換える・変える」と書く。
※構文の型についての記載は省略しています。
つまり、「買い替える」は、「か・える(他下一)」の❸が、該当することになるでしょう。ただ、この説明からすると、一般的には「買い替える」でも「買い換える」でもよいことになりそうです。また、「買いかえる」において、「変える」を使うことはないはずです。
なお、「か・える(自五)」は、❶【返る】、➋【帰る】、❸【反る】、❹【孵える】です。
用例で「買い替え」としている小型国語辞典についてのまとめ
『記者ハンドブック』や『最新用字用語ブック』と同じような立場を取る小型国語辞典として、『三省堂国語辞典 第七版』(見坊豪紀・市川孝・飛田良文・山崎誠・飯間浩明・塩田雄大, 2014年1月10日発行)、『新明解国語辞典 第七版』(山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・山田明雄・上野善道・井島正博・笹原宏之, 三省堂, 2012年1月10日発行)、『岩波国語辞典 第七版新版』(西尾実・岩淵悦太郎・水谷静夫, 2011年11月18日発行)があります。この3冊では、「買い替え」という表記のみを載せています。
この3冊は一般社会人向けの小型国語辞典のため、いずれかを所有している方が多いのではないでしょうか。しかし、3冊ともあまり厚みがないので、省略したり使い回しのきく漢字を優先したりしているという見方もできます。新語の採取に力を入れている、あるいは、用例主義的な態度とも言えそうです。実際に同じ出版社が発行している中型国語辞典、『広辞苑』(岩波書店)や『大辞林』(三省堂)では、両方の表記を載せています。
また、3冊を比較すると、用例に使われている漢字にずれが生じています。
「かいかえ」については取り上げていない国語辞典
『ベネッセ表現読解国語辞典』(沖森卓也・中村幸弘, ベネッセコーポレーション, 2003年5月初版発行)では、「かいかえ」という見出しはありませんが、「か・える(変える・代える・替える・換える)」を重要語として取り上げ、複数の用例を示しながら、以下のように解説しています。
【変】❶形・性質・内容などをそれまでとは違うものにする
【変】❷場所や期日などを別の所や日時に移す
【代・替】❸ある役目を別のものに担わせる
【換・替】❹もとのものを捨ててそれと同種の別のものを用いる
【換・替】❺あるものを相手に与え、それと同等の別のものを受け取る
用例のなかに複合動詞はありませんが、「買いかえる」に関しては❹が該当し、「買い換える」と「買い替える」の両方の表記を認めていると考えてよいでしょう。ただし、【代・替】❸の用例では「代」、【換・替】❹❺の用例では「換」を使用しています。また、「代える」と「換える」を入れ替えることはできませんが、「替える」については両方の言い回しに使えます。
さらに、『ベネッセ表現読解国語辞典』の漢字部を開くと、「換」については、あるものを別のものとひきかえる、物のやり取りをする、物を金に換える、という使い分けの説明がありました。「替」については、あるものを別の物と入れかえる、あるものを新しいものと入かえる、社長を替える。
『学研現代新国語辞典 改訂第三版』(金田一春彦, 2002年4月1日発行)において、「かわる・かえる」の使い分けに関する記述がありました。
換える〔物をとりかえる〕金に換える・名義を書き換える・部品を取り換える・バスを乗り換える
替える〔ある物にかえて別の物と交替する。古いものから新しいものにする〕商売を替える・新しい水に替える・投手を替え(代)る・新しい服に着替(更)える・家を住み替える・借金を振り替える・荷を持ち替える
更に続けて次のような記述があります。
「換」と「替」はしばしば混用され、かなで書かれることも多い。また「替わる」は意味が近似するところから、よく「代わる」と書かれ、厳密な書き分けは困難である。
『角川必携国語辞典』(大野晋・田中章夫, 角川書店, 1995年10月27日初版発行)にも、「かいかえ」の項目はありません。「かえる」の項目を見ると、『記者ハンドブック』や『最新用字用語ブック』などに近い語釈でした。【換える】の解説が、他のものととりかえる、交換する。【替える】は、前のものをやめて新しくする、という解説です。そして用例は、【換える】が「金に—」と「代金と引き—」、【替える】が「商売を—」と「たたみを—」でした。
さらに手元にある9冊の国語辞典の中で、もっとも発行年度の古い『旺文社国語辞典 改訂新版』(松村明・山口明穂・和田利政, 旺文社, 1986年10月20日発行)を引いてみました。「かいかえ」という言葉は載っていませんので、「かえる」を調べたところ、「代える・替える・換える」の使い分けが載っていました。次のように書かれています。
「代える」は、あるもので他のものに間に合わせる意
「替える」は、あれとこれとが交替する意
「換える」は、物と物とを取りかえる意
“かえる”の表記、どこでどう分ける?――用法と語源をめぐって
“かえる”と読む言葉の中でも、とくに判断に迷いやすいのが「替える」と「換える」の使い分けです。本章では、両語の意味や用法の違いを整理しながら、辞書の記述や語源的な背景にも目を向けつつ、表記の選び方についてもう少し踏み込んで考えてみます。
『漢字源』で「替」と「換」の意味をチェック!
次に、「換」と「替」という二つの漢字を、『漢字源 改訂第五版』(学研)を参照しながら比較してみます。
『漢字源』には、「換」の意味について次のように記載しています。「かえる、かわる、中身をすっかり入れかえる、取りかえる、入れかわる」。そして交換という熟語が例示されています。
「換」は会意兼形成文字です。まず、会意文字の側面で述べると、「換」の原字である「奐」は、女性のしゃがんださまと、両手を組み合わせた会意文字です。
「奐」は、胎内から胎児を取り出すさまを表しています。「奐」の上部が両股を開いた女性のさまで、下部が両手です。この「奐」という字は、ゆとりをもって、まるく抜き取るという意も含みます。
次に形成文字の側面について述べます。「換」は意符「手」と音符「奐(カン)」の組み合わせです。音読みは漢音が「カン」で呉音が「ガン」です。
「替」の意味については「かわる、次のものと入れかわる」と「漢字源」に記載されています。この場合の同義の漢字は「代」。交替という熟語が例示されています。
「替」には、「かわって、身代わりとなって」という意味があり、のちに「だれだれのために」という意味にもなります。「おとろえる、すたれる」という意味もあります。
さらに日本語特有の意味として「かえ、身がわり、代用品」という意で使われるようになりました。
「替」は、夫(おとこ)ふたりと、日(動詞の記号)を組み合わせた会意文字です。「替」は、Aの人からBの人へ入れかわる動作を示しているのです。音読みは呉音が「タイ」で漢音が「テイ」です。
つまり、「換」は女性の出産シーンに関係し、「替」は人が入れかわる動作ということです。漢字の意味を根拠に判断するのは難しいようです。ただ、「換」が新たに生み出されることであり、「替」が入れかわることと解釈すると、「かいかえ」の表記の判断にも生かせそうです。
『ブリタニカ国際大百科事典』における”用語”としての扱い
CASIOの電子辞書「XD-SX6500」を所有していて、生活関連のコンテンツとして『ブリタニカ国際大百科事典』を利用できます。そこで、「かいかえ」について検索したところ、「買替え需要」「買換え特例」「買い替えローン」がヒットしました。
「買替え需要」とは、「耐久消費財を買い替えるときに発生する需要のこと」で、1980年末から90年代初めの好況時の高級化指向の説明にはじまり、不況による買替え需要のストップが経済の足を引っぱる悪循環に陥ったことの解説で締め括っています。
しかし『デジタル大辞泉』では「買い換え需要」とし、【買(い)換え需要/買(い)替え需要】という表記も加えています。
「買換え特例」は「居住用の不動産を買換える際の譲渡益に課税しないという制度」のこと。国の制度であり、国税庁では「買い換えたときの特例」という記載があります。民間でも概ね「買換え特例」ですが、大手をふくめて「買替え特例」としている不動産会社もあります。
「買い替えローン」は「正式な融資が実行されるまでのつなぎとして借り入れる短期ローン」のこと。「住み替えローン」ともいい、ほぼ「替」の字が使われていますが、「買い換えローン」の表記も見られます。
「部品をかえる」という場合の漢字を考えると…
故障などで「部品をかえる」という文言を使うときは、どちらがよいのでしょうか。
「換える」が、他の物ととりかえる、交換するという意で、「替える」が、前のものをやめて新しくするという意だとすると、「部品を換える」としたほうが適切です。部品を交換するといいますから、「部品を換える」のほうがしっくりくるのではないでしょうか。
例えば、『最新用字用語ブック 第7版』においても、用例として「部品を換える」を載せています。
ただし前述した通り、『広辞苑 第七版』には、複合動詞の「取り替える」の用例として「部品を取り替える」という文があります。「取り替える」に関しては、「替」のほうが適切ということでしょう。
逆に、『記者ハンドブック』と『最新用字用語ブック』においては解釈が異なり、交換というニュアンスがあるためか「取り換え」としています。
また、「とりか・える」に関しては、多くの国語辞典において「取り替える」と「取り換える」の両方を記載しています。
文語形はハ行下二段活用の「かひかふ」
「かいかえる」という言葉にはそれなりの歴史があり、文語形では「かひかふ」です。この事について中型国語辞典では、『精選版 日本国語大辞典』『大辞林 第二版』『大辞林 第三版』では触れていました。『広辞苑 第七版』では「かひかふ」には触れていませんでしたが、「かふ」については触れていました。小型国語辞典でも、『明鏡国語辞典 第二版』『新選国語辞典 第十版』などでは、「かふ」だけでなく「かひかふ」にも触れていました。『学研現代新国語辞典 改訂第三版』『旺文社国語辞典 改訂新版』では、「かふ」についてのみ記載がありました。
「買い替える」と「買い換える」を使い分けるとしたら
「買い替える」と「買い換える」を使い分けるとしたら、漢字の意味の違いを深く理解する必要があるでしょう。ただし、国語辞典や漢和辞典でさえ、「替」と「換」の使い分けは紛らわしい場合が多い、混用されることが多い、といった記載があります。
「替」と「換」には「かえる」という意味があります。国語辞典によっては、「替」については「あたらしくする」という語釈を加えています。
さらに、「替」には「すたれる・おとろえる・他にとって代わられる」という意味が加わるという違いがあります。
こういった点が、ふたつの漢字の使い分けに関係してくるはずです。
自動車販売店や家電量販店などは、新しくするというニュアンスが影響すると「買い替える」となるのかもしれません。小売店はメーカーから仕入れて、お客は使えなくなったり古くなったりしたものを処分し、新しく購入します。自家用車を買い替えるや、冷蔵庫を買い替えるなどです。
カー用品販売店において、「タイヤ交換」に加えて、「タイヤを履き替える」という言い回しが用いられるのは特筆すべきでしょう。もちろんエンジンオイルについては、「オイル交換」のみです。
どちらかというと「替」が「互いにいれかわる、前のことをやめて別の新しいことを行う」、「換」が「他のものととりかえる」とうニュアンスです。「替わる」が「入れ替わる」、「換わる」が「交換・転換」の意であるため、「替」は人にも使われます。多くの場面で「交替」という熟語が例示されます。「換わる」は「ものが相手に渡って別のものが渡される、つまり交換」のニュアンスが強まります。
自動車販売店や家電量販店からすると、金銭のやり取りはありますが、交換するわけではありませんので、「買い替え」となるのでしょう。
よって、報道界では「買い替え」と表記し、『三省堂国語辞典』『新明解国語辞典』『岩波国語辞典』においては、「買い替え」のみを載せるという結論に達したのかもしれません。
「替」と「換」の違いについては、漢和辞典のほか、類語国語辞典や漢字字典の要素が加わった国語辞典であれば、同様のことが記載されています。対象を中学生から一般社会人ではなく、高校生から一般社会人にしているほうが、相対的に詳しく触れているはずです。
日本語における漢字表記の宿命とTPO!?
この「買い換えると買い替える、どちらの漢字が正しいのか」という漢字表記の選択に関しては、結論付けが難しいようです。
辞典類で確認したところ、「買い換える」と「買い替える」の両方が載っている場合と、「買い替える」のみを載せている書籍に分かれます。新聞の広告・チラシや大型小売店のポスター、テレビ番組のテロップなどでは「買い替える」の表記が増えているので、最近は「買い替える」のほうが見慣れているかもしれません。
しかし、「代える」と「換える」を入れ替えることはできませんが、「替える」については両方の言い回しに使えます。「替える」は「換える」よりも幅広く使える漢字です。そのため、「買い換える」のほうが的確という見方もできるでしょう。実際に官公庁の文書や小説など、どちらかというと硬い文章では、「買い換える」が使われています。
また、作家や書籍編集者などの間で「買い換える」が使われていることを考えると、使い回しのきく漢字として「替える」が多くなっただけなのかもしれません。