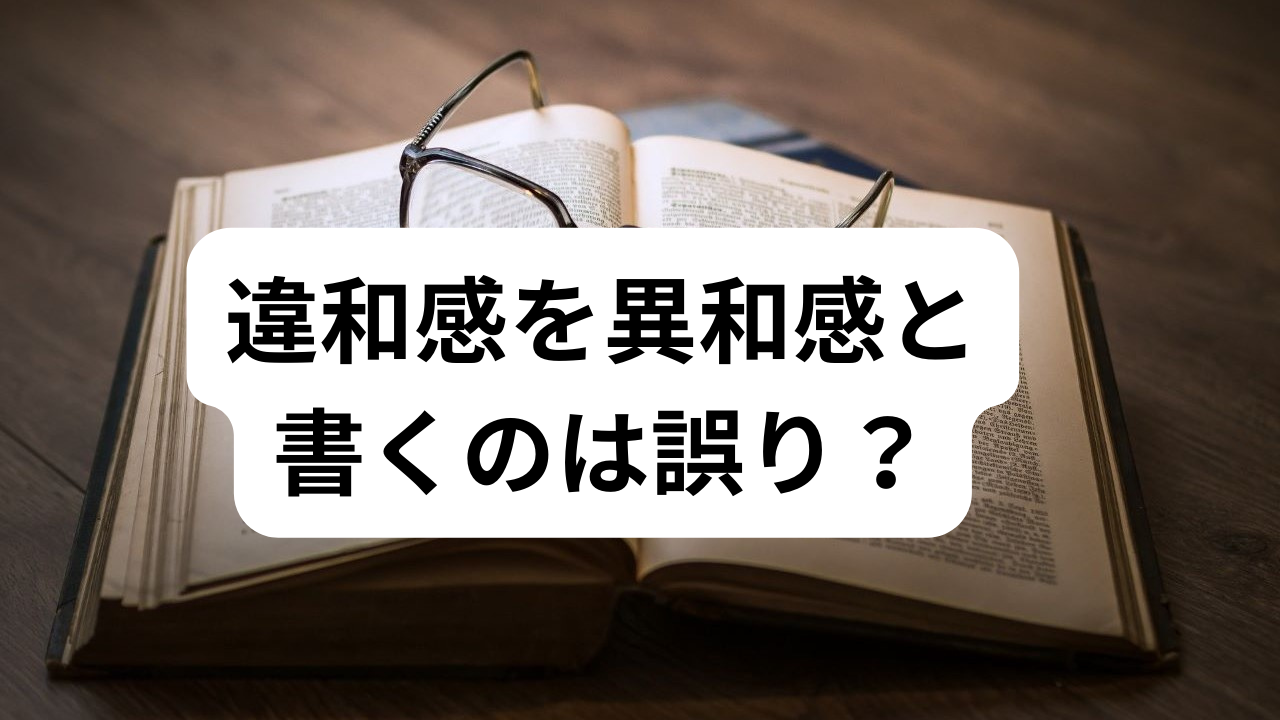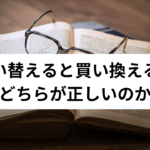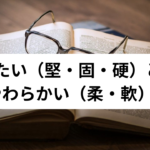「違和感」を、「異和感」と書いている文章を見ることがあります。一般的には、「違和感」と書くのが正しいと言えるでしょう。この文章をWordで書いていますが、同音語誤りと指摘されます。
けれども、「異和感」という表記が誤りとは、必ずしも言い切れないようです。国語辞典の中には、「異和感」を認めている辞典もあります。11冊の国語辞典を参照したところ、見出しはすべて「違和」という表記でした。
ただし、11冊の内の3冊は、「異和」という表記も認めています。その3冊とは、『新明解国語辞典 第七版』(三省堂, 2012年1月10日発行)と『新潮現代国語辞典 第二版』(新潮社, 2000年2月5日発行)と『精選版 日本国語大辞典』(小学館)です。
特に『新明解国語辞典 第七版』は、「異和」という表記の使用について、詳しく解説しています。この表記の可否については、本書の解説がもっとも参考になるでしょう。まず本書では、「違和」という言葉には、二通りの意味があることを説明しています。
一つ目は、体の調子がいつもと違って、どこか具合が悪いこと。二つ目には、対象を素直に受け入れたり、環境に自然に馴染んだりするのに抵抗を感じること、と書かれています。そして二つ目の意味で使う場合は、「異和」とも書く、としています。
『新潮現代国語辞典 第二版』でも、「異和」とも、と表記を認めています。本書は、明治から現代までの七万九千語が収録されている辞典です。
用例の採集は、辞書類・小説・評論・詩・童謡・新聞・雑誌など。文学的な用例の豊富さが特徴の辞典です。出典の信頼度は高く、出典の明示もあります。生き生きとした用例は、作例より参考になることも多いでしょう。
『新潮現代国語辞典』は、昭和60年(1985年)に第一版が刊行され、平成12年(2000年)に第二版が刊行されました。明治初年(1868年)以後百三十年におよぶ日本近代の言葉が、どのように成り立ち、どのように使われてきたのかを回顧できることが、大きな魅力といえるでしょう。
ただし『新潮現代国語辞典』は、残念ながら絶版のようです。平成22年(2010年)に増刷されましたが、令和3年現在、品切れとなっています。増刷や改訂の予定はなさそうです。
『精選版 日本国語大辞典』には、「違和感」の項目に、「異和感」と書かれることもある、という補注があります。「違和」の項目では、「異和」という表記に触れていません。
『精選版 日本国語大辞典』は、『新明解国語辞典』と同様に、「違和」の語釈を二通りに分けています。一つ目は、心身の調和が失われ、調子が変になること、または病気にかかること。二つ目は、雰囲気にそぐわないこと、または二つのものが調和しないこと。そして「違和感」については、調和を失った感じ、他と合わない感じ、しっくりしない感じ、という記述です。
一方、「異和」という表記を誤りとする辞典も多いようです。『大辞林 第三版』(三省堂/アプリ版 スーパー大辞林3.0)、『明鏡国語辞典 第二版』(北原保雄, 大修館書店, 2010年12月1日発行)、『角川必携国語辞典』(大野晋・田中章夫, 角川書店, 1995年10月27日初版発行)、『類語国語辞典』(大野晋・浜西正人, 角川書店, 1985年1月30日初版発行)では、「異和」や「異和感」を誤りとしています。(『大辞林 第二版』では「違和」と「違和感」の記述のみで「異和」という表記には触れていません)
さらに、『記者ハンドブック 第13版』(共同通信社)や『最新用字用語ブック 第7版』(時事通信社)においても、「異和感」を誤用としています。原則として「異和感」という表記を使わずに、「違和感」と書き換えるという指針です。
『広辞苑 第七版』(岩波書店)、『岩波国語辞典 第七版』(岩波書店)、『三省堂国語辞典 第七版』(三省堂)、『ベネッセ表現読解国語辞典』(ベネッセコーポレーション)では、「違和」や「違和感」の解説のみで、「異和」という表記には触れていません。
『広辞苑 第七版』では、「違和」について次のように解説しています。体の調子が破れること。転じて、他のものとしっくりしないこと。ちぐはぐ。そして「違和感」は、ちぐはぐな感じ。『広辞苑』は、簡潔で分かりやすい説明ですね。
以前は、「異和」という表記も使われていました。しかし、現在は誤用扱いされてしまうかもしれません。今後、文章を書くときは、素直に「違和」と書くべきでしょう。