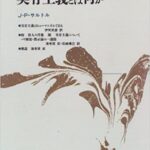清水良典氏の著書『あらゆる小説は模倣である。』を紹介します。
目指すのはエレガントな模倣への道
清水良典氏の『あらゆる小説は模倣である。』は、2012年7月に幻冬舎新書より刊行された。どんなジャンルであれ創作とは、見様見真似から始めるものだから、模倣という言葉はそれほど違和感のあるものではない。けれども、自作を世に問う段階になると、違反行為のような性質を帯び始める。「あとがき」によれば、本書を執筆するきっかけは、幻冬舎から「盗作になることなく他の小説をサンプリングして小説を書く指南書は書けないものか」という依頼であったそうだ。
悩みながら考えたが、なかなか書き進められずに、二年が経ってしまう。そして、ある確信が育った。「ひとは単独で創造するのではなく、人間が永い歴史のなかで育んできた豊かな蓄積に支えられている」と考えるようになった。本書の題名は、こういった考えから付けられているのであろう。模倣でなくとも、たいていは先人からの影響を受けているものだ。
「盗作」や「盗用」の疑惑が持たれ「パクリ」呼ばわりされてしまうのは、他の作品をなぞった下手な模倣。場合によっては、二番煎じや紋切り型に陥った無知な模倣も疑われかねないリスクがあるだろう。もちろん、本書ではそれを進めていない。
本書で指南するのは、「もとの作品を土台にして別個の作品にしあげてしまう巧みな模倣」である。そして、あらゆる小説は多かれ少なかれ、他の小説から影響を受けていることを、清水氏は読者に伝えようとしている。その事実から出発し、「巧みな模倣」の道を明らかにしようとした。
小説の模倣について考えるうえでは、文学理論や文学史などの知識も必要であった。清水氏は、なにも自説ばかりを主張しているわけではない。近代以降に世界に広まった理論や具体例を基に立証している。そのため、文学理論的なことも多くのことが学べる。文豪のことや、名作がどのように書かれたのか、さらに現代の状況についても触れながら、あらゆる小説は模倣であるということを示した。
近代においては、翻訳の文体が、日本の作家に大きな影響を与えた。外国語を翻訳した文章は、日本語と文化の土壌が異なるため、見つかりやすい。日常の文章の延長では、どんなに工夫を凝らしてもありきたりになるが、その壁を一気に打破するには、外国の文章に触れることが手っ取り早かったようだ。ご存じのように、近代日本における欧米諸国からの日本語への影響は、現在の日本語に受け継がれている。
ひとは同時代の表現の習慣や型に束縛され、その時代に広まった言葉はさまざまなジャンルで氾濫し、しばらくたつと、今度は批判的な文脈も姿を表す。このように、テキストはその時代に影響され束縛されてきた。
世界的な小説家や近代の文豪でさえも、影響というよりもむしろ模倣といえる作品が見受けられる。たとえば、村上春樹氏の『風の歌を聴け』であれば、アメリカ人作家カート・ヴォネガット・ジュニアの『スローターハウス5』。夏目漱石の『吾輩は猫である』であれば、19世紀ドイツの作家、E・T・A・ホフマンの『牡猫ムルの人生観』。
また、近代日本の文学史において、文豪の盗作疑惑が検証されてきた。それは、資料からのほぼ丸写しであったり、経験者の記録をリライトしたものだったりするのだ。近代においては、元ネタから小説を仕立て上げるという行為が日常的であった。弟子や出版社が雇った作家による代作もあった。もちろん、本書ではこういった事をすすめているわけではない。
異質の文体を学び、真似ることで、大きな変化と成長を遂げるかもしれない。しかし、盗作のそしりをうけるという、怖い落とし穴がある。とくに小説の世界では、盗作や盗用はむろんのこと、無断引用や著しい類似でさえご法度。
たしかに、似ている程度では、たやすく白黒をつけられるものではなく、著作権侵害には当たらないかもしれない。しかし、注意を払う必要があるので、本書には著作権に関することも詳しく書かれている。現代の盗用疑惑事件のことも書かれている。重要なことなので、本書を読んで確認していただきたい。
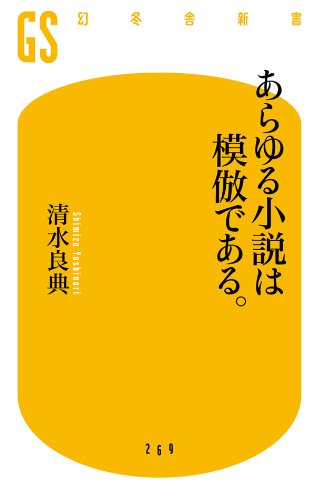
書誌情報
書名:あらゆる小説は模倣である。
著者:清水良典
出版社:幻冬舎(幻冬舎新書)
発売年月:新書 2012年7月/電子書籍 2016年2月
ページ数:新書 234ページ
Cコード:C0295(日本文学・評論・随筆・その他)