 書物とことば
書物とことば 『暁の宇品 陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』堀川惠子 船舶輸送の実態と司令官の苦悩
『暁の宇品 陸軍船舶司令官たちのヒロシマ』は、2021年に講談社より刊行されたノンフィクション作家・堀川惠子さんによる著書。本書は第48回大佛次郎賞の受賞作。船舶輸送の実態と司令官たちの苦悩や葛藤について知ることができた。
 書物とことば
書物とことば 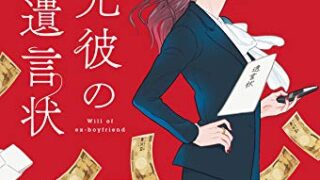 書物とことば
書物とことば 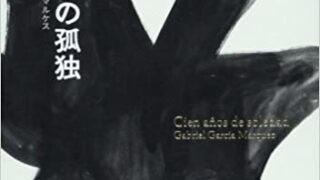 書物とことば
書物とことば 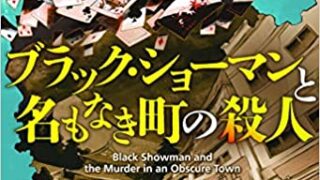 書物とことば
書物とことば 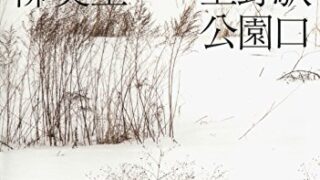 書物とことば
書物とことば  書物とことば
書物とことば 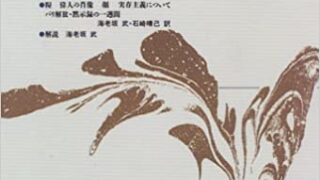 書物とことば
書物とことば  書物とことば
書物とことば  書物とことば
書物とことば 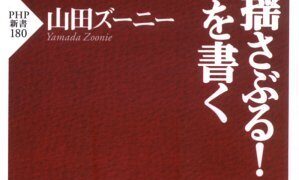 書物とことば
書物とことば